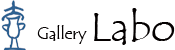この小出作品に、これまで見ることがなかった薄造りの盃は、平安期の瓦器碗を想起させるものであったので氏にそう述べたところ、そのイメージであるとのことでした。
高台脇から口辺までが一定の厚さで内面は「ミガキ」によって整えられているところなども瓦器的手法です。
しかし、そういうことよりもこの深く豊かな焼成りはどうでしょう。派手さと渋さとが共存する中世的な良さが出ているのです。
口径を数字だけでみると、大きく感じられるかも知れませんが形状からすればこれがちょうど酒を呑むのに適格な大きさと容量です。
また、酒を入れた瞬間、見込の胡麻色が劇的にパッと明るくなる、という演出もしてくれます。
使ってみたい、という欲求に関しても今回の作品群のなかでも私的には上位に入ります。
本当は私が欲しいNo.13の手付酒注に合う酒盃を、と小出氏にリクエストして選んでもらったのがこの盃なので一対で持っていただけると嬉いな、とは私の勝手な望みです。