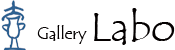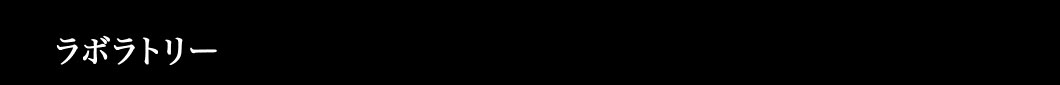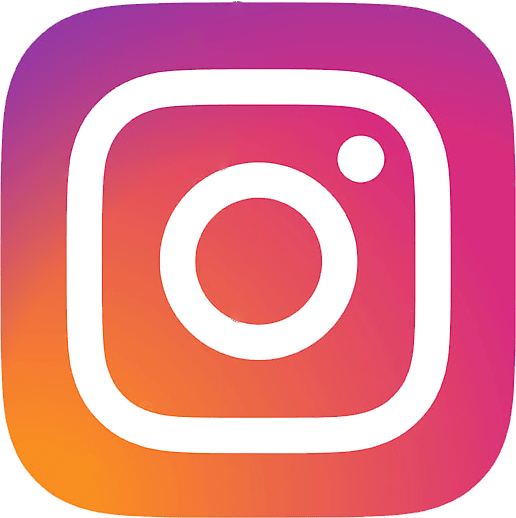2. 信楽蹲 14世紀 高さ14.4cm
新設のこのコーナーですが、二回目の今回は第一回に引き続き室町期の信楽、「蹲(うずくまる)」です。
この手の小壺が「蹲」と呼ばれる由縁は、「人が蹲っているように見えるから」ということだそうですが、見えますか?
大きさとしては高さ四寸から七寸くらいまでの小壺で、胴径に比して底径が広いのが特徴です。(ちなみに同時期の大壺では胴径に対しての底径はずいぶん狭く、これは陶磁史のなかでも平安末期の常滑や鎌倉初期の珠洲に次ぐ相対比なのです。第一回の大壺をご参照下さい。中壺はその中間です)
この蹲の本来の用途に関しては、古くから種壺といわれていました(正しくは「種浸し壺」でしょう)が、そのなかでも小振りのものは、中世から近世にかけてのその他の古窯の小壺と同様に「お歯黒壺」とも呼ばれ、実際に現在でも内部にお歯黒を確認できるものが随分ありますが、これは江戸期など後世になってからの転用である場合が多いので、これらのすべてがお歯黒用に作られたわけではありません。
ここで紹介する蹲も当初、内部にお歯黒が酸化鉄状に層を成してこびり付いていて、私の使用目的は主に酒注ぎですので、金ブラシで時間をかけての除去を試みましたがそう簡単には取れず、未だ随分残っています。最近ようやく酒を入れても鉄の味がしなくなりました。
この蹲の特徴は、姿と土肌、そして酒に使える大きさと酒切れの良さ、さらには呑むたびにはからずも鉄分の補給まで出来ることです・・・。
特に姿は、「これぞ信楽蹲!」と断言してもよいものです。この形が中世信楽蹲の典型です。
さらに焼き成りにも二つの典型がみられ、まずひとつは灰の被り方です。灰被りの様相は窯の構造、窯詰めの方法、また作品の素材と窯の焚き方などによって様々に変化します。
この時期の信楽には他にはあまり見られない独特の灰の被り方と質感を持ちます。ここで紹介している蹲の灰被りは、前回の大壺と同様、中世信楽特有のものです。
そして二つめは、その肌合いです。これは信楽の命と言って過言でないものですが、この蹲のこの焼き肌こそが先人達の「信楽で死ねる」との言葉をしみじみと感じ取れる肌合いだと思っています。
この蹲で酒を注いで呑んでいると、束の間の幸福を覚えすぎて酒量は適量をはるかに超えたりするのと、同じく先人達が「うずくまる ねだんをきいて うずくまる」と詠ったように、厳しい「蹲相場」というものがあり、通常であればうずくまっておしまいです。ですがこういうものと出遭ってしまうと、それが年収の半分であろうと三分の二であろうがそんなもん知るか!という具合になりますので、「信楽で死ねる」という言葉は、「信楽で死ぬる」と化して真に迫って来るのでした。
追記として
壺の「口」の作りについてですが、その「立ち上がり」が外反するものは時代を遡り、直立し口縁の「玉縁(たまぶち)」の大きなものは時代が下る(新しい)、という従来からの説がありますが、確かに総体的に各産地ではそのような傾向があります。(これまでに紹介した二つの壺は「外反口縁」です)
外反するものも、直立玉縁のものも、ともにその成り立ちは「壺にふたをする」といういたって機能上の理由によるものです。
塩化ビニールやポリプロピレンなどの石油由来の素材が無かった時代、布を被せて紐で縛ることが、もっとも手っ取り早く「蓋をする」方法でした。外反のものは頸の付け根、玉縁であればそれが紐掛りとなります。
製作技法からみれば、「外反」のほうが「直立玉縁」より自然なのですが、後者の方が形状と強度の面から、使用の際に破損するリスクは軽減されます。
リスク回避のため自然から不自然に向かう流れも、「現代人類」のほぼ終末期といえる不自然さをみるかぎり、自然なことかもしれません。