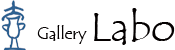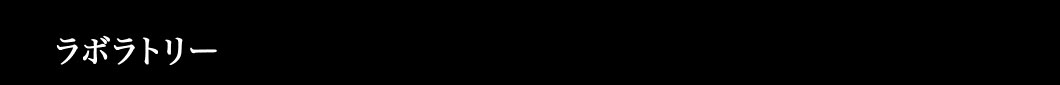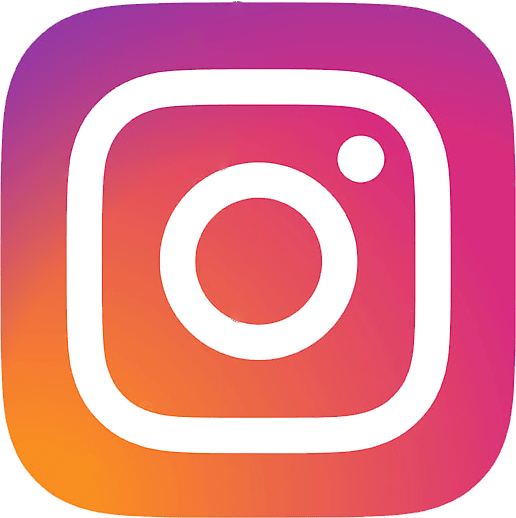徳利を選ぶときの要点の話です。
徳利は「姿」です。
一見したとき、その姿が気に入りさえすれば、あとは酒切れが悪かろうと、暴力的に重かろうと、少々漏れようとも、そんなことを気にしていては一生の損です。
姿が悪い徳利は、いかに機能性に優れていようが、焼き肌が美しかろうが、手取りが良く使い勝手がよかろうとも、無理して使っていたところで早々に我慢の限界はやってきます。
「姿」には造形だけではなく、品格というやっかいな要素も含まれます。
「姿の良さ」の基準は見る者によって違うように思われがちですが、やきものに限ったことではなく「ある水準以上」のものには普遍性というものがあり、好き嫌いは分かれても、本当に良いものへの評価はさほど分散しないものです。
徳利は姿が命です。
以上が、徳利を選ぶ上で大切なことの話でした。
で、終わるには、あまりに不親切であるような気がしてきましたので、“その他細かいこと”なども余談として付け加えておきます。
口穴の大きさ、頸部の内径のことでは、「小指一本入るくらいが良い」といわれているのをよく耳にしますが、これは“徳利好き”の感性ではありません。
徳利は姿の次に、酒の「出かた」と「出音」がとても大事なものです。
“小指がものすごく白魚”でもないかぎり、小指が入るような内径であれば酒は実にだらしのない軌道を描き、その出音も締まりなく、酒の始まりの間合いが随分間抜けなものとなってしまいます。また姿の上でも、胴径の割に首の太い鈍重なものになりがちです。この呪文に多くの気の毒な作者が引っ掛かり、その造形を破綻させています。
この手のものの利点としては、酒を一升瓶から少々入れやすいのと洗いやすいことくらいですが、徳利を使う楽しみは半減します。
あまりにも狭いと酒を入れようとしても逆流して、使いみちが「水滴」くらいになりますが、容量が二合五勺以下のものであれば通常、鉛筆一本入るくらいから“普通の白魚”程度の小指では、無理に入れると当分抜けなくなるくらいまでが適切な口穴の大きさです。
次に、徳利の「酒切れ」の話です。
酒注ぎには、上から注ぐもの(徳利など)と、横から注ぐもの(片口など)とに大別できます。
徳利の場合、注ぐとスパっと一滴残さず切れられると、要件だけ伝えていきなり切れる電話のように味気も余韻もないものです。
徳利の理想は、注ぎ終えると一、二滴垂れてそれが肩で留まるものです。ただし垂れ方にも品性の有無が問われ、ただ垂れればよいというわけではありません。
一滴も垂れない“酒切れの良い徳利”を作るのであれば素人でも簡単なことですが、上の条件をみたすものを狙って作るには多少の技術を要するのと、まずはそのイメージが必要です。切った際、僅かの間口辺に留まった一滴がその直後スーっと直下して、肩のあたりでピタりと止まるイメージです。これは大切なところです。
因みに、片口など横に注口があるもの(急須なども該当します)の場合は、一滴たりとも垂れないことが理想です。これのキレの悪いのは、ダラダラと続く不毛な会議やエンディングでコケる小説のようなものです。
横口のものは切れが良いに越したことはありません。
次に、「漏れ」についてです。
磁器のもの以外、土もので荒目に製土されたものや石ハゼのあるものなどは、水漏れの生じることが多いものです。
特に原土の良さが生かされた質感が際立つものには、その確率が高まります。使う側が漏れを嫌うと通常撥水処理が施されてしまい、やきものの命である“水利き”が著しく損なわれます。よくありがちな悲しい現実です。
問題は「どの部分からどの程度漏るか」ということです。
入れた酒がそのまま直通で卓に広がってゆく、というのはさすがに酒がもったいないどころか呑めないのでいけません。また三分の一呑んだはずが半分に減っている、というのもなかなか呪わしいものです。
これらの場合は、下に片口で受けておけばよいのですが、徳利が風呂に入っているような光景となり、別の趣きとしては楽しいのですが、徳利の姿を楽しむには障りがあります。
理想は上半身からまんべんなく、酒が露骨に減らない程度の分量が漏れてくる徳利です。
これに当たると徳利は常に潤いを保ち、ときおり擦り込んでやるとよく育ちます。
ややこしそうですが、徳利をこのように作ることは可能ですので、制作者の方達にはぜひ試みてもらいたいものです。
徳利が全く漏らないということの取得は、無難であることくらいです。
徳利が漏ることを極度に嫌がるのは現代病です。
このことと関連しますが、焼成が甘い徳利は内外に黴がはびこり、いちど居座った黴の生命力と忍耐力たるや、こちらが羨ましくなるほどのものです。
煮沸したくらいでそう簡単には撤退せず酒を入れた瞬間「カビ酒」になり、これがまた不味いのです。徳利の肌も黒や緑色に彩られますが、これがまた美しくはないのです。
「生焼け」の徳利は、あとで面倒なのが嫌な方は避けておいた方が賢明です。
さていよいよ「徳利の重さ」についてですが、これは茶碗やぐい呑より少々ややこしいものです。
まず、“手重り”と“重量”は別のものです。
茶碗、ぐい呑などと同じく重要なのは手重りですが、徳利の場合はその重心がどこにあるかによって、同じ重量のものでも手重りは大きく変化します。
しかも内容量が茶碗、ぐい呑より多く、空の場合と酒の入った状態とで、その重心は一献注ぐたびに変わり続けます。
まず注意点は、空の状態で「重い」と感じてもあまり気にしないほうがよいということです。購入を考える場合は、水を入れてもらって実際に少しずつ注ぎ出してみることをお勧めします。
もとが「重い」徳利のほうが満量時の重みは気にならないものですが、空になっても手重りがあまり変わらないので呑んだ実感には乏しく、酒量制限中の方には不向きかも知れません。三合くらいは入るかと思えば一合二勺しか入らなかった、という凄いのもあります。
「重量が軽い」徳利は、手重りの変化はわかりやすいものの、「徳利の手重り」というよりも「酒の重量」といった感となり、手取りの感覚を楽しむには頼りないものです。
重量の軽い徳利は薄造りですので、見かけよりも酒がたくさん入り、やはり酒量制限中の方には不向きです。
重さに重点を置くならば、“重心”に留意して選ぶことをお勧めします。肩に重心が来ている徳利であれば、酒の内容量を問わず手取り感がそれほど狂わないことと思います。
器壁の厚みが均等な徳利は、重心が分散してしまい、手取り感を楽しむには不向きです。
また重心が腰に寄り過ぎていると、いわゆる「尻の重い」ものになり、盃へ傾ける度、ちょっとした手首の運動にはなるかもしれません。
李朝初期や琉球の江戸末のものには一瞬怯むほどの重さのものも多いですが、毎日三合ほど呑んだら腱鞘炎になったという話はあまり聞いたことがなく、肝炎になったとしてもそれは徳利が重いせいではありません。
徳利を楽しむための最良のコツは、重さは気にしないことです。
徳利の重いことを極度に気にするのは現代病です。
補足として、古い時代の徳利をもとめる際の注意点は油臭の有無です。とくに李朝や江戸末期のものには油徳利として使用されていたものが多く、この油臭はそう簡単には抜けはしないのに、酒を入れると瞬く間に臭いが酒に移ってしまいます。普通に使っていても10年や15年では抜けません。油を呑み続けることになります。
古い徳利を購入の際には熱めの湯を入れてもらい、三分たって湯を捨てると臭いを確認できます。この油臭は抜けないわけではありませんが、状態によってはそれなりの手間と時間がかかるものです。
良い徳利の条件をまとめてみます。
1.姿の良いこと
2.「出口」が広すぎないこと
3.正しく漏ること
4.注ぐと酒が一、二滴垂れて肩で留まること
5.生焼けでないこと
6.適度な手重りがあり、重心が肩にあること
7.古陶磁の場合、油臭のないこと
ですが何といっても、やはり徳利は「出合い頭」です。
姿を見た瞬間「これだ!」と感じたものが「それ」なのです。
いろいろ考えずに、「それ」を選ぶのが賢明なことと存じます。
後はどうとでもなるものです。
“支払い”のことは知りません。