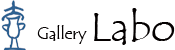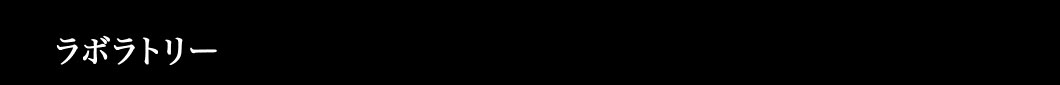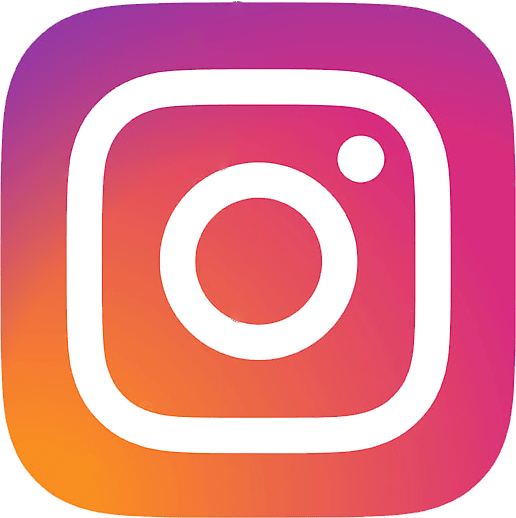ーまえがきー
本稿は話の性質上、基準の具体性が必要と思われる場合、やや専門的な用語を使わざるを得ない箇所もありましたので、難解に感じられる場合は読み飛ばすか用語をお調べ下さるか、あるいは本稿そのものを見なかったことにして下さい。
やきものが「しっかりと焼き締まっている」のには、概ね次のような要因があります。
有史以来のやきものを通して割合の多い順に並べてみますと、
- 原料(土と釉のことです)の耐火性が低い。
「“よく焼き締まっている”から焼成温度が高く、焼成時間も長い」と考えるのは早計です。実際そのように、たとえば「SK8(1250℃)以上!」、「一日や二日程度ではない!」など(2時間もあればやきものは充分に焼けますが)と言う人が少なくありませんが、実際にそのような「高温、長時間」に該当するやきものは歴史または世界全体の中でもごく一部のものにすぎず、大半は低温域で充分焼き締まる素材を使い、最小限の時間で焼成した様子がその現物から確認できます。 - 原料(特に土のことです)の炭素に対する反応性が高い。
中国紀元前の黒陶、戦国時代の土器、韓国百済、新羅、高麗などの土器、日本の須恵器とその流れを汲むもの、などがあのように厳格に浸炭を試みた理由は「黒いやきもの」ではなく「強靭なやきもの」を目的とした結果であると思われます。現にそれらは焼成温度が前出のゼーゲル「SK6(1200℃)以下」のものが大半であるに拘わらず、酒の臭いも染み付かず黴の発生もほとんどなく、“やきものダニ”(焼の甘いやきものに好んで生息する優秀な品質検査ダニです)もいません。やきもの焼成において最重要点は、炭素の操作をおいて他にありませんが、素材によって炭素に対しての反応性が異なります。備前陶の素材などはその反応性の高い代表で、焼き成りの変化の細やかさもその理由によるものです。 - 焼成あるいは冷却時において、分子構造の変換される“変態点”の通過回数が多くそれが分子間結合力を高める組み合わせとなる場合(ただしその方法によっては、より脆弱となる場合もあります)。たとえば、いかに焼成時間を長くかけてもただ「ゆっくり上げてゆっくり冷ます」のみでは変態点の通過回が数少ないものです。「焼き締まり」には通常一般的に言われることの多い焼成時間や最高温度、あるいは総カロリー量などよりも、どのようにこの変態点を通過させたかによる影響が絶大で、2.とも強い関連性を持ちます。
- 少数の例外としては、たとえば古伊賀などのように比較的高い温度で焼かれたと予測させるものもありますが、いずれにせよ“高温”や“長時間”だけでは、弾力を感じさせる強靭なテクスチャーは得られません。
近現代のやきもののほとんどが、近世以前の古陶とは明らかにその質感を異にし、「生焼け」でなければ「ただ固いだけ」であるのは、1.~3.についての誤解、または無理解によるものと思われます。また、ただ固いだけのやきものが「良く焼き締まっている」と思われがちなのは現在では、「古陶」「現代陶」などと分別せず共に熱心に愛好する者が激減の一途を辿っている残念かつ悲しい現実によるものと考えられます。これまで何度も述べていますが、上記のような「古陶」「現代陶」との分け隔ては、見る側作る側ともに、百害こそあれ全く利の無いことです。存命中の者が目にするものは、当人にとってすべて現代の出来事ですので、やきものは総て「やきもの」でよいわけです。それぞれの「販売店」が異なるのは単に警察署の都合にすぎません。
話を戻し、上記の1.について少し説明を加えておきますと、無駄に時間と手間をかけそれを喜ぶのは機械文明に飽きた近代人くらいのもので、古人の仕事の精巧さからその手の余分や無駄を見出すことは困難で、やきものもその例外ではありません。
せっかく低火度で堅固に締まる素材があるのに、わざわざ現代人のように知ってか知らずか本来サヤに使うような耐火土で茶碗を作り、高温長時間焼いた挙句充分に焼き締まらず、それに気付くこともなく表面の見てくれのみで出荷し、使用すれば短期間で汚れ果てることを主客ともに「味」と言って喜ぶような愚行の痕跡を、古人の仕事からは確認できません。いかに低温短時間、より少ない労力で堅固なものに仕上げるかの工夫が随所に見られるのはごく当然のことと思われます。
余談ですが、鎌倉時代中期まで全国シェアNo.1であった常滑陶に備前陶が取り代わって席捲した理由は、港湾の整備による海上交通、政権の変遷といった類のこと以上に、低温焼成で堅固な製品を量産可能な「備前の土」による影響について、この方面からも充分に考慮する必要があります。備前陶の素材とその製法は、上記の1.~3.のすべてにおいて好条件を満たしており、ちょうどこの頃からの生産体制の変化がその製品や窯の立地からも伺えます。
現在この国のやきもの業界で、さほど疑われることもなく常識となり収まっている「伝統の製陶法と言われているものとその発想体系」略して「伝統」は、相変わらず明治以降にドイツより移入されたものが基調となっています。近代ヨーロッパ産業革命以降のいわゆる「近代文明」を経て、戦後日本の高度成長期の反動である農村回帰の副産物、あるいはその出来の悪い兄弟のように生まれたカウンターカルチャー「陶芸」ですが、その弊害といえる無駄な手間暇の成果が「重厚な焼き味」などと有難がられるのであれば、重厚すぎる皮下脂肪などももっと多くの人々に喜ばれるべきものでしょう。
先述のように古陶磁の愛好者が現代陶を「新モノ」と言って相手にしないのは、「クラシック以外音楽ではない」などと言う者と同じくその者の偏狭さと感度の悪さが主要因であるにせよ、やはりそれは残念なことなので、現代陶に潜む何かしらの問題を検証してみなくてはなりません。
その結果「作者の人品」はさておいて特に目立つのが、作品の志向性に適切な技法選択の誤りまたは単なる無知によるもので、「焼成技術」もその中で主なもののひとつです。
商品として販売する以上「現代作家」さん達にはもう少し、技法を含む“やきものの研究”を進めていただきたいものだと思う今日この頃です。
つづく