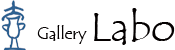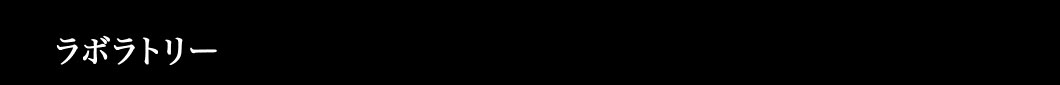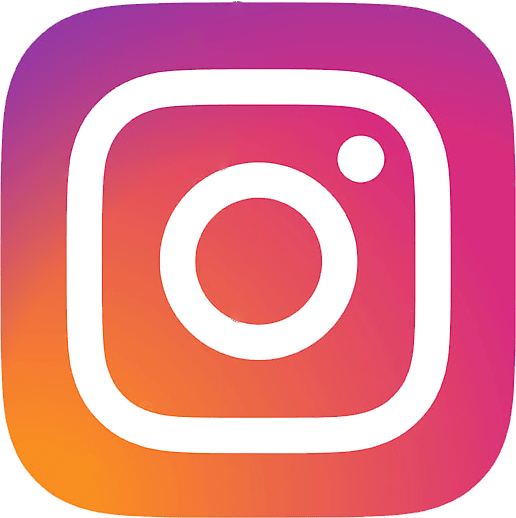茶を喫する際に茶碗を少し回して正面を外す、という現在では常識化された作法について、「江戸末期まではそのような作法は無く、回したりせずに出された正面からそのまま飲んでいた」という説があります(引用文献は記さないでおきます)。
「常識を疑うぞ!」という姿勢には大いに賛同できますが、では遡ること桃山期の「沓茶碗」などはどうやって飲んでいたのでしょうか?
沓形茶碗の造形は一辺の長い三角形あるいは楕円形を成し、例えば黒織部などでは長辺の最も広い面に窓絵がありそこが正面となっているものが大半です。
この真直ぐ一直線となった“正面”からそのまま茶を喫するには口角間の長さが少なくとも15cmほど必要で、そのような該当者は「オバケのQ太郎(古くてすみません)」か「口裂け女(古くてすみません)」か「カバ(躙り口から入室できません)」くらいしか思い当たりません。あの京唄子さん(古くてすみません)でも無理でしょう。沓茶碗には、正面を外した鋭角となる部分に、更に飲み口となる箆目が切られているものも多く見られます。これらは正面から左右に回せば飲み口が現れ、常人でも容易に飲める構造となっています。このような造形の茶碗が量産されるのは、当時から回して正面を外して飲むことが前提であったからです。志野茶碗(当時から存在する「模造品」は除く)なども正面の側面に飲み口があり、その位置まで回すと腰部が掌に収まる構造となっています。
冒頭の説の論者さんによれば、「茶碗の正面を外して飲むと記載された文献は江戸末期まで無い」というのがその論拠だそうです。「文献に無いことは実在しなかったということではない」というのは考古や歴史学の基本にして常識なのですが、ついでにそれも疑ってみたのでしょうか?
今回はわかりやすく簡単な実例をひとつ挙げてみましたが(こういった例を文献とその著者を挙げてゆけばけっこうな分量となりますが、このコーナーは「常識は疑え!」であって「おととい来やがれ!」ではありませんので“常に穏便に”を心掛けています)、絵に描いたような机上の空論が近年増々まかり通る「陶磁研究」といわれる分野は、とにかくまずは一次情報である「モノそのものを見る」という絶対基礎から始めてもらわないと、結局誰の役にも立たないだけでは済まず間違った情報がウイルスのように蔓延します。こういったものを読んで鵜呑みに信じてしまう抗体を持たない愛好者や業界関係者は実に多いのです。陶磁研究家と言われる人達のモノそのものを見る力量は、この国家そのものの力量と同様もの凄い勢いで衰退していますが、これに気付かないのは更に恐ろしいことです。「見ているようで観ていない」は“素人さん限定”で許される特権なのですが、知識やデータは増える一方で観察力や熱意は衰えるという傾向は用を成さない空洞化の典型です。
やきものと国政との関係性はいつの時代でも深いものでしたが、政界や財界のリーダーたちの素養が凡庸あるいは低俗と化した現代では、やきもの業界の劣化や観光化の現況も不可避なのかもしれません。
胆力のみならず語彙力も退化した政治家たちの言葉を借りれば、「これはいかがなものかとたいへん遺憾であるので抜本的に骨太な改革を しっかりと進めていただきたい」ものです「な」。