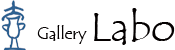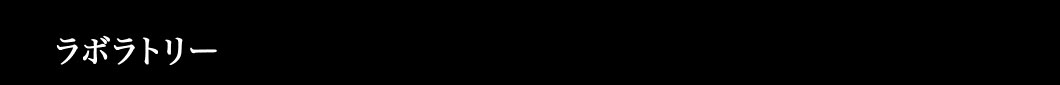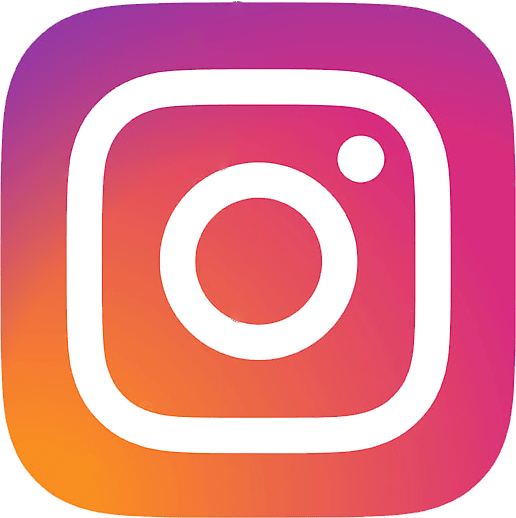ふた世代ほど以前には、日常の中でやきもののことを「せともの」「からつ」と呼ぶ人は少なくありませんでした。現在でも、そのことをご存じの方は多いかと思います。
主に東日本では「せともの」、西日本では「からつ」(こちらには“もの”がつかないのが一般的です)、と呼ばれる傾向にあったとのことです。
これについて、「せともの」は瀬戸(現愛知県)、「からつ」は唐津(現佐賀県)なので東西でそのように俗称が異なるという説があります。
この一見何ら問題なさそうな“やきものの常識”のひとつであるこの説に、疑うべき箇所があるとすればいったいそれはどこでしょうか?
やきものに少なからず興味を持つ方であればすでにお判りのことと思いますが、今回はこれについて少々述べてみます。
たしかに私の祖父や祖母(ともに西日本)たちは、やきものをすべて「からつ」と呼んでいた記憶があります。因みにその後の世代では、全国的に「せともの」のほうが断然多くなったようです。
ここでは、その「からつ」とは何であったか?について検証してみます。
「からつは唐津のことであろうが」と通常は片付き、これまでそれについて触れた文献にも大概はそう書かれています。
その名が俗称として定着するには、その地域に数多く長期にわたり普及していることが条件のひとつです。
16世紀末より出現した唐津は文禄から慶長期に隆盛を迎え、広域流通もしていましたが有田で磁器の出現の後に「唐津」と呼ばれているものは急速に衰退します。この時期で注意すべきことは、広域流通したといえどもその対象は武家屋敷や豪商であり一般家庭は含まれません。近代以降は唐津市周辺で現在の「唐津焼」に連なる展開となりますが、西日本の家庭に「唐津焼」が広く普及したという話は聞いたことがなく、知る限りにおいて西日本のどこの家庭でも見かける肥前のやきものは、「有田焼」であって「唐津焼」ではありません。
因みに「せともの」である瀬戸のやきものは、美濃焼と共に近代以降現在も全国津々浦々の各家庭に普及していますので、こちらの呼称は今でも広く一般に使われているようです(やきもの愛好者には案外使われません)。
それではなぜ、西日本で「からつ」はやきものの代名詞であったのでしょうか?
西日本在住の人々が広く「古唐津」の熱烈な愛好者であった、などということは西日本在住の大半は火星人であったのとほぼ同じ確率です。
このままでは謎は深まるばかりですね。
では時代を曾祖父たち世代へともう少し遡ってみましょう。この世代の西日本の人たちは、特定のやきもののことを「かがつ」と呼んでいたそうです(私も幼少期には実際に何度もそれを目撃しています)。
何を「かがつ」と呼んでいたのでしょうか。
「かがつ」と呼ばれていたやきものの正体は「擂鉢」です。
擂鉢であれば、近年までは大概どこの家庭にもあったものです。
「かがつ」がそのうちに、名前だけは知られていた「からつ」と訛ってすり替わったのでしょう。
ですがまだ疑問が残ります。
なぜ擂鉢が「かがつ」なのだ?ということです。
やきもの愛好者の方々はもうお解りかと思いますが、「かがつ」の正体は備前擂鉢のことです。
中世に全国シェアを席捲した備前のやきものは、中でもその主力商品であったのが擂鉢でした。その後江戸も半ば以降に地場産業として衰退してゆくのも、明石や堺で備前擂鉢の安物コピーが量産されたことが大きな要因でした。
そして、備前のやきものの中世における通称は現在のように「備前」ではなく、またそれ以前の「伊部」でもなく、「かがつ」でした。
「かがつ」は当時のその一帯が香登ノ荘(園)であったことにより、現在は伊部に隣接し香登(かがと)という地名として残ります。
14世紀半ばに記された今川了俊の「道行きぶり」より引用すると「さて、かがつといふ里は家ごとに玉垂れの小瓶といふものを作る所なりけり。山の峰越しの松のひまより、海少しきらきらと見えておもしろし」ということからも、「かが“津”(港湾)」であったかも知れません。江戸中期にもやはり擂鉢が山陽道四国方面で「かがつ」と呼ばれるとの記載があります(「物類称呼」)。
そのようなわけで擂鉢は、たとえ備前産のものでなくとも「かがつ」と俗称され、西日本にはそれが末永く根付いた後、いつしか「からつ」に成り代わったのでした。
現在では「すり胡麻」などもスーパーやコンビニで売っており、「かがつ」を備える家庭も少なくなりました。
やきもの好き以外に「からつ」と言っても通じず、やきもの好きは「からつ」とくれば反射的に古唐津の酒盃や茶碗を思い浮かべるものです。
ですが今回は「からつはじつはびぜんでした(-ω-)/」、という話でした。