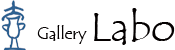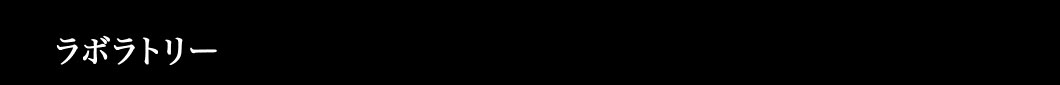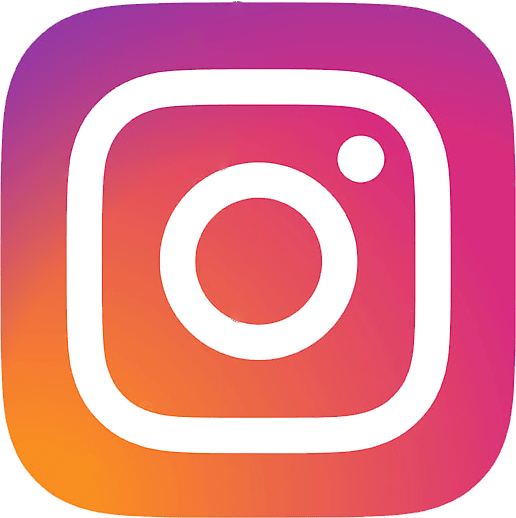やきものは芸術かそれとも科学か?という問いがあるそうです。
こういった問いは、イヌは哺乳類かそれとも愛玩動物か?という類と同じものです。
やきものは、窯から出て来るまでは作成者の意図に関わらず全ての行程に科学が関与しますが、窯から出た後、それが芸術か商品か不燃ゴミかなどという区分は、見る側の外にはありません。
また「芸術」というのは大変曖昧な言葉で、仮にそれを「人間の深層意識を表層で認識し得る形をとるもの」あるいは「芸によって人心を動かす術」とすれば、営業職、水商売、ヤクザ、政治家の街頭演説、水族館のアシカなど、かなり広範囲で多くのものが該当することになり、ならばわざわざそのような紛らわしい括りをつけることもないわけです。「芸術」「アート」などという言葉を不用意に乱用していると、大概その人格を疑われるものです。
よって冒頭の問いに対してはイヌと同様、「接する者の都合と勝手」ということになります。
よって以下は“あとがき”ですが、途中が少々長く読んでもあまり役に立たない場合が多いかと思いますので、面倒なかたはここから最後へ飛んでいただければ・・と思います。
先述のように、やきもの製造という行為には、その作者の認識の有無にかかわらず、どのような手段を取ろうが、土の準備から窯焚き冷却まで否が応でも終止「科学」は常時付いて回りますので、ここでは「やきものと科学」について少し考えてみることにします。
やきもの作成の作業行程は、まず作るものに合わせその素材である土(または石)を選び製土する作業から始まり、それが終わると成形し乾燥させ窯に入れて焼成し、手入れ検品後出荷となります。
これらはその他すべての工業製品と同様ですが、最も大きく異なる点は、現代のやきものは便器や碍子部品などを除き、特に「陶芸品」と呼ばれるものの検品基準が生産者、取扱店、消費者ともに他ではまず有り得ないほど甘いことくらいです。
なぜそういうことが長らく罷り通っているかといえば、「陶芸品」は世間一般にとって生活必需品ではなく嗜好品の中でも市場規模、認知度ともに低いもの、つまり国家にとっては有ろうが無かろうがどうでもよいものであることが主要因です。近世以前はそうではなかったのですが、現代の国家のしくみでは全くどうにもならないことです。
その近現代に、科学が質量ともに注力されるのは国家や団体にとって有益なこと、つまり「金になる」ことです。「陶芸」は付加価値に惑わされる人々を騙す能力にでも長けていない限り、決して「金にならない」ものです。ほんとうですよ。
また、仮にそういう手段で「金にした」ところで、政治家や官僚、経団連あるいは反社会的組織などがそれを利用して資本投下し元が取れる規模ではまったくありません。
というわけで、「やきものの科学」(「窯業の~」ではない)に公費や企業資金が投入されることはなく、研究の必然性を問う提案が出ることも、おそらく今後も人類がいちど滅亡するまでないでしょう。
さてそれでは「やきものの科学」とは、どの段階にどういう形で存在するものを指すのでしょうか。
他の工業製品と同じく、やきものの作成行程にもすべて存在する「科学」ですが、そのなかで特に制作者がそれに直接意図して関わる必要性があるのは、製土、成形、窯詰め、窯焚きの四工程です。
まず「製土」とは、山などから掘り出した土を木槌で叩いて(現代ではスタンパーやミルなどの機械もあります)篩に掛けたり、水簸したりして目的の製品に合致する状態に整えることです(この工程を行なう前の掘ったままの状態を原土と呼び、その状態で使用することもあります)。
ここで人為によって「科学」に関与するのは「土の叩き方」です。
どういうことかといえば、土は岩石の風化したものですので、叩いて行くとまずは風化の進んだ部分から砕けてゆきます。そうして残った未風化の堅い部分や小石は、同じ母岩であれば風化部分より耐火度は低いのが常です。小石でも耐火度の高い珪石は木槌で叩いたくらいでは微粉にはならないので、土の“焼き締まり”をより強くする場合には残った小石を構わず砕いてゆきます。先のスタンパーを使ったりミルで摺って粒子を細かく揃えた場合、珪石も砕け耐火土はまた再び上がってしまうので、結局木槌による手作業のように微調整ができず、「より非科学的」となるわけです(もちろん目的を特定せず無闇矢鱈に叩きまくるのは、更に非科学的ですが・・)。
このように原土を叩いて粒子を細かくする作業により、後に窯に入れて熱処理(窯焚きのことです)の際の素地のあらゆる反応に多大な影響をもたらしますが、現代の「陶芸家」の多くが、土の性質を大きく左右する「土叩き」の重要性を甘く認識していることも、また「非科学的」な事実です。
次に「成形」です。
やきものの成形手法としては轆轤挽き、紐積み、手捻り、たたら合わせ、刳り貫き、泥漿鋳込みなど様々にありますが、すべてに共通する重点は「水の使い方」であると言えます。
「粘土」は土質力学の分野で粒子が5μm以下のものを指し、粒径がそれ以上のシルトや砂と区別されています。
そこに「水」を含む場合、同じ体積であれば粒度が細かいことにより各粒子が纏う水(自由水と呼ばれます)の総量が上がり、これによって「粘り」つまり可塑性が生じるわけです。砂に粘性や可塑性が無いのは粒度が大きいからです。つまり粘土の「粘」の正体は水であり土そのものではありません。それが証拠に乾けば砂同様に全く粘りを失います。
さてここからですが、そういうわけで成形時には土に含まれる水の状態が、同じ土で同じ形を作った場合にもその表情のみならず、乾燥から焼成まで後々に大きな影響を与えます。
ですから、ここでも焼き上がりから逆算して成形や削り、装飾などの際に素地中の水分を意図してコントロールする必要があります。たとえば轆轤挽きの際には土の含水量と手水の量、削り成形時では「乾燥具合い」によって成形直後のみならず焼成後の表情がまったく違ってくるものです。
さてその次には「釉薬」についてですが、「やきものの科学」というと真っ先に連想されやすいものがこの部分かと思います。
上皿天秤を前に厳格に調合する様子は、やきもの以外の場合であれば科学的な光景かもしれません。
ですが、やきものの場合ではそれはたいへん非科学的な光景に見えます。
なぜならば、釉薬に使用する土石はたとえ同じ場所から採取したものでも、いちいち成分が異なるからです。天然の土石は1メートル四方の中でもずいぶん成分が異なるものです。
したがって「データを取って毎回正確に調合」する、ということは即ち「確実に毎回異なる結果を生む」こととなります。適当に目分量で放り込んだ方が、まだ当たる確率は確実に上がるわけです(この作業もあまり出鱈目にやると競馬で大穴を当てる確率より下がるかもしれませんが)。
焼成時の昇温データなどもこれと同様で、毎回窯内や外気など諸条件が毎回異なるにもかかわらず、「良かった」ときのデータを使うと確実に「それ以外の結果」となります。そのようなデータが有効とするには、まずは毎回全く同じ作品(寸法、厚み、素材)を寸分違わず同じ位置に詰め、焼成の最初から最後まで同一条件である必要があり、万一それが揃ったとしても今度は窯や窯道具の状態が前回とは必ず異なりますので、「同一条件」になることは絶対にあり得ません。従ってこちらも「前回と同じ結果」が必要なのであれば「前回と異なる方法」が必須となります。
このくらい当たり前のことが、現代ではなぜか認識されていないようです。
絶望的な気分となる話ですが、「釉薬が決まる」と焼成条件が少々異なろうが何とかなるものです。その逆はありません。
ですから、ここは人間としての諸感覚を駆使するより他に良い方法はありません。
釉薬の調整は、やきもの作成行程で、最もっとも科学が介入するようでいて最も科学を使ってはいけない部分なのかも知れません。人間がかりに100種類の原料を調合したところで、そこら辺の土石を適当に拾って焼くだけで遥かに複雑で深みのある質感を得られるので、所詮は人為により精製した原料をどれだけ重ねても「そこら辺の土石」には桁違いの諸成分が含まれ、またそれが正しく作用するということです。
「そこら辺」をどこに見極めるかが人間内の天然の科学であり、これを安定して成功させることが「芸術」であるかもしれません。
「人為をで推し量れない」といえば、真っ先に“窯焚き”を連想される方の気持ちはわかりますが、実際に“窯焚き”は全行程の中では比較的「人為でどうにかなる」作業で、圧倒的に「ならない」代表が釉薬の調合です。人為で何とかできるのは、せいぜい原料の選択までです。
これに気付かず明治以降の輸入された「釉薬の調合」という発想体系で製陶を続けた結果、近代では「窯業製品」は発展するも「やきもの」は後世の考古学者に見られるのが恥ずかしいほど無残に衰退したわけです。釉薬は「その辺の石に灰を少々」が最良の結果を生むわけですが、これも科学の領域ですべて解明しようと思えば何とかなりそうな気がしますが、費用対効果という観点からすれば、アホくささの領域が芸術的となります。
次が「窯詰め」です。
この作業がやきもの制作一連の作業中、最も重要で出来上がりへの影響の大きな作業です。
いかに造形が良くとも「焼き上がり」がダメだと、ダメなやきものとなります。
その「焼き上がり」に、焼くという作業である「窯焚き」以上に影響力を持つのが「窯詰め」です。
窯詰めが正しく出来てさえいれば、誰が焚いてもある程度のものは出来ますが、これが出来ていなければ“窯焚き名人”がどのように焚いたところで、所定温度には焼け上がりますが「ダメなやきもの」となるものです。「ひと窯焚いて良いものは数点」などと臆面もなく言い放つ“陶芸家”は、その「数点」も大したしたことがないのが常ですので、この窯詰めの手法を発想からやり直すことを勧めます。
「窯詰め」という言葉は実際には不適切で正しくない言葉なのです。これがどういうことかと言えば、窯詰めされた状態のみが「窯」であるからです。
熱や煙や炎が走るのは窯の内側であって外側ではありません。
例えば、家の中には間仕切りがありますが、家の中を移動する際には間仕切りに従った動線となります。家具や電化製品などの生活用具を据えれば更に動線は細かく設定されます。
これと同じことです。
通常、多くの皆さんが「窯」と呼んでいるものは「窯の外枠」にすぎません。壁と天井です。
人間からしてみれば「窯とその中に窯詰めされたやきもの素地」かもしれませんが、中で実際に働く熱や煙や火からすれば知ったことではなく、窯も作品もすべて同じく窯です。
ですから「窯に作品を詰める」という発想は間違いで、正しくは毎回窯焚きのたびに「築窯」という作業を繰り返しているわけです。
よく「窯焚きは、まずは窯本体が作品より先に充分に焼けるよう温度を上げよ」という陶芸家を見かけます。かなりそれらしく聞こえますね。ですが、こういう人が「ひと窯で数点」なのは、先の理由により「窯に作品を詰めた」と考える時点ですでに間違えているからです。
もう一度繰り返しますが、「作品」は焼き上がって窯から出すまでは「窯そのもの」なのです。
例えば桃山時代の備前の50メートル級の大窯には、後の登り窯のように間仕切りが無いので、巨大な穴窯だったと考えられていて、これを再現しようとする人もいるようですが、これはとても短絡的な発想で無駄に薪と時間と労力を消耗し、当時の大窯は実際には一定間隔で大甕などを積み重ねて「壁」を築き、それを間仕切りとなる登り窯であったわけです。
しつこいようですが「窯詰め」という作業は、「窯に作品を詰める」のではなく、「作品で窯を構築する」のが正解です。窯の壁や天井も作品も、すべて同じ「窯」なので、それらの輻射熱によって温度が上がってゆくわけです。やきものは決して「炎」で焼くのではありません。炎そのものは薪を燃やした折りに生ずる副産物にすぎず、やきものを焼くのに直接関与しない不要物ですが、これも意外なほど知られていないことです。やきものの焼き上がりは「熱と水素と炭素の化学反応」であり、決して少なくとも「炎の芸術」などではありません。
こう言えば必ず、「昔の人は科学に頼らず経験と秀でた勘で焼いていたので良いものが焼けたのだ」という人がいますが、「昔の人」をバカにしてはなりません。「科学」というものが系統だって認識され発達する近代以前は、人間が動物としての天然の科学力を持ち得ていた時代です。
「昔の人にもこれだけのことができたのか」と、たいへん吞気な感心の仕方をする人が少なくありませんが、正しくは「昔の人だからこそできた」わけで、比較可能な全ての物事はどこからどうみても「昔の人」の方が圧倒的に優れています。
科学が発展したから人間力が劣化したのか、人間力が低下するなかで科学の発達という必然性が生まれたのか・・・・いずれにせよ、その使い方を誤ったことで「現代人」は今や地球史上最悪の生物と成り下がったのでしょう。
前置きが長くなってしまいましたが、窯詰めに科学が関与するのは、中に詰める「窯の部品(作品)」によって熱対流や輻射熱または内圧の状態が大きく変わり、結果として「作品の焼け具合い」が異なる、ということです。「外枠」である窯の壁、床、天井も、同じく毎回表情を変えてゆくものです。
さて最後に、やきものは窯焚きを経て初めてやきものとなります。
「焼く」という行程を経て化学反応のパターンが決定された結果が「やきもの」と呼ばれるわけです。
そのようなわけで、窯焚きは中でもとりわけ科学に関するものの出番が目立つ作業工程です。
まず最初の行程は「あぶり」という作業です。窯焚きの際に「加持祈祷」や「斎戒沐浴」などの儀式がそれに先立つ人もいますが、それはあくまでそういった行為が日常ではなく「イベント」となった 近現代人ならではの各自の趣向によるオプション(「苦しい時の神頼み」とも言う)であり、どちらかといえばあまり「科学的」でもなさそうでのでここでは省きます。
「あぶり」の目的は、最初の変態点(分子構造が変わるポイント)である三百度前半から半ばに到達するまで、急熱により内部の物体に極端な温度差をつけないことが目的です。このポイントを急熱で飛ばしてゆくと破損率が高まります。
逆に言えば、「あぶり」の際にはこの幾つかの変態点の前後の昇温のみに注意してさえいれば、現代大半の作家(特に備前)がやっているような、明らかに無駄な多くの時間や燃料そして労力を使う必要がないのです。
またこの段階を「湿気抜き」だと思われていることの多いのも現代の特徴です。先述のように窯焚きには湿気つまり水素が必須ですが、必要なだけの湿気を常に保つのも技術のひとつですので、この時点でそれを抜いてしまうのは実に勿体ないことです。ひとつだけ具体的にあげれば「湿気は抜かずに下に降ろす」ことが肝要ですが、通常このようなこともその方法も「やきものの作り方」の本には一切書かれていませんし、内弟子修行などに入っても教わることはないようです。
次に行程を少し早送りし、「酸化、還元」と呼ばれ、よく知られていることについての話です。
「酸化で焼く」、「還元で焼く」というのは、実際には雑で正確に欠く言い回しです。
「酸化、還元」という化学反応そのものについて、ここで述べようとしているのではありません。
ただ、その言葉をそっくりそのまま「やきもの」に使うには実際には無理があります。
その詳細を述べることはここではあまりにも長くなってしまいますので、一例のみ簡略して挙げておきますと、薪窯では酸化と還元は必ず混在し、ガス窯や電気窯で「純酸化焼成」を行なった場合には、還元状態を経なかっただけのことで「酸化」させたわけではありません。やきものにおける「還元」とは、素地や釉材に含まれる酸素を取り除くこと、「酸化」とはその状態から再び、文字通り酸化させることです。酸素が窯に入れる前と同じ状態やバランスであれば「酸化」したのではありません。
要約すると、「還元焼成」とは窯内のある一定温度域において酸化物質から酸素を取り除き、その状態を保った状態で焼き上げること、「酸化焼成」とは窯内のある一定温度域において酸化物質を一度還元状態にした後、再び酸素と結合させるが、元の酸化物質へ戻すわけではなくその加減により目的の色や質感に仕上げることです。還元を経ない場合には本来「酸化焼成」ではなく、正しくは「還元ナシ焼成」です。
よく「還元焼成のほうが難しい」という人がいますが、それは昇温の容易さに関してのことと、厳格な還元状態が大気中では生じにくいということで、前者は昇温の技術を身に付ければよく、後者は窯の隅々まで厳格に還元状態にする必要などない、ということで容易に解決されますが、「酸化焼成」の場合は先述のように還元状態からの酸化させる加減で「やきものの品質」が大幅に左右されます。これはたいへん重要なことですが、「酸化」で片付けてしまうと元も子もありません。
したがって「いかに良いやきもののを焼くか」に重点を置くと、酸化焼成は還元焼成とは全く比較にならないほど難易度は高いといえます。
やきものは、温度を上げさえすれば何かしらのものは焼けますが、「温度を上げるのが難しい」などと言われてみて見れば、昇温方法が誤っているなど初歩的はことを除けば大概は「窯の構造」が悪いようです。
ここまでお付き合い下さった方ならばすでにご理解のこととは思いますが、かなり重要な一大事ですので念のため繰り返しておきます。ここで言う「窯の構造」とは、「窯の外枠」に「作品」とよばれるものが内部に構築され終えた状態のもののみを指します。通常一般に「穴窯」「登り窯」などと呼ばれている「外枠の構造」を指してはいません。
余談として、現在では通常内部に幾つかの間仕切りがある窯を「登り窯」、間仕切りのない単室のものを「穴窯」と呼ばれています。
「穴窯」の構造の最大の長所は、窯内温度や「窯内雰囲気」と呼ばれる酸素、水素、炭素の分布状態に大きな差異があることです。これを「短所」ととらえ窯内雰囲気を揃えようと悪戦苦闘している作者をよく見かけますが、そのような作者には「穴窯」は向きません。ですが、先に述べた方法で「穴窯」を「登り窯」にすることが出来ます。近世以前ではよくある手法でした。
ではその逆で間仕切りのある「登り窯」を「穴窯」に換えることは、間仕切りを破壊しない限り出来そうにないようにも思えますが、こちらは“焚き方”によって火の流れ(熱対流)を穴窯に近くすることであれば可能です。もちろん“窯詰め”を併用することで効果が増します。ですが、先のパターンに比べれば効果やそうすることの意味は少ないものです。
穴窯が登り窯に移行したのは、熱効率の改善であるというのはよく聞く通説ですが、それだけではなく、それ以前に比べ作品が小型化したことも“知られざる”要因のひとつですが、その根拠は上記の「間仕切りに大型作品を使用していた」理由によります。
「穴窯から登り窯になって効率を追求した結果、雅味を失い良いものが焼けなくなった」という“定説”などもありますが、それは間違いです。移行させた当時は「良いものが焼けない」のではなく、「焼くものの需要に対応させた」だけで、選択肢がある近現代では「焼こうとするものに焚き方を含めた窯のセッティングが合っていない」だけのことです。この場合「窯のセッティング」とは、窯の内部構造とその素材を目的に合致したものに合わせるという熱対流のコントロールのことです。その当時には生産目的から窯の構造を割り出し、それに合致させた良いやきものを焼き出しています。穴窯時代と同じものを狙った痕跡はいずれの産地にも見られず、これを「やきものの良さ」という基準で比較はできません。ならば、現在穴窯で焼く作者のやきものに「良い」ものの方が少ないのは如何なる理由によるものでしょうか。
話が少々逸れますが、「科学」という分野には然るべき「科学誌」が存在し、そこに科学者の作品である論文が掲載されることで実力が認められ研究の発展にも繋がるようですが、対して「陶芸」と呼ばれる分野には、不出来な同人誌のような出版物がいくらかあるに過ぎず、下手にそこに掲載などされようものならば私たち業者やまっとうな愛好者からは軽んじられる、という現状は何を示すものなのでしょうか?「趣味の分野だから」というのは言い訳にはなりません。音楽、愛玩動物、乗り物などを始め、同じく趣味の分野である多くの出版物は、いずれもそれに関わる者の造詣や熱意に尋常でないものを感じられますが、なぜか「陶芸」となれば素人が選んだミソクソ混同の作品と、同人達の冴えない身内話に終始しているに過ぎないのですが、そのことに気付かぬ同人作家や読者と彼らに向け単なる広告雑誌として利用する業者とで成り立っているようです。科学誌のように、実際に優れた者達が掲載を望み、業界の進歩に寄与するような媒体の出現が切に待ち望まれます。
窯焚きに関してはもうひとつ、非常に重要なことでありながらも広く認識されていないことを簡単に述べて本稿を終えます。
「やきものを焼く」ものの正体は炎ではなく燠(おき)ですので、燠をコントロールする技術こそが即ち窯焚きの肝要であるということです。炎をただ当て続けたところで真っ当なやきものにはなりません。
また、窯の中の状態は「炎を見る」のではなく「炎の隙間を見る」ものです。窯内の色で見る際の「温度」も同じく、発光する炎ではなく熱による色温度のことです。その際に炎は、邪魔な副産物以外の何ものでもありませんので、それに惑わされないこともまた技術のひとつです。
因みに、薪や石炭など固形燃料の場合以外はガスや熱によるカロリーで素地や釉の分子構造を変換させる作業を「焼く」と呼んでいます。薪など固形燃料のほうが不確実かつ複雑な要因が多く、それが良いほうに働けば薪ならではの効果が得られますが、焼き成りのイメージが明確にありそれを実現させる技術を持つ場合には、ガスや電気炉による方が「良いやきもの」になる確率が上がります。近代以前は薪や石炭を燃料とする窯しか無かっただけで、もし当時ガス窯しか無かったとすれば、薪窯志向など持たずにやはり良いやきものを焼いたと思います。ガスや電気炉だから物足らない焼きになると考える作者は、単に技術や技法において乏しいからそうなるに過ぎません。
やきものを焼くことにおいての科学は、動物として本来備わる「天然モノ」を使うのが理想です。ですが、「天然モノの科学」を失うことでの反作用として現代の人智による科学体系が発達しているとすれば、天然モノを失った現代人としては、知識としての科学をあくまで道具や手段として使うことは有効です。「長年の勘」というものには案外、天然モノではない「科学知識」が意図せずとも含まれているものです。
「つまらないやきもの」であれば、人智によっても無知によっても簡単に量産が可能です。「稀にみる良いやきもの」ほど不確定要素や不純物が幅を利かせているためしばしば人智を越え、その解明を試みた結果、科学より神仏に頼るしかないという挙句に「芸術」という発想へ安直に行き着くのかも知れません。
因みに、そういった「不確定要素」の解明を試み「不純物」という雑な括りをせずその実体を顕すのが科学だとすれば、哲学や芸術と呼ばれてきたものも同様の手法を必要とする人間の所産です。
冒頭に戻って本題です。
やきものは、少なくとも決して「土と炎の芸術」などではありませんので、そのような警察や地方自治体が得意とする出来損ないのキャッチコピーのようなものは「風紀を乱す」のでいい加減止めませんか?という話でした。