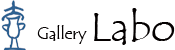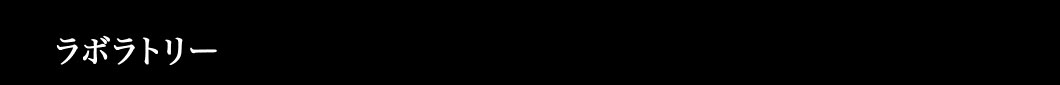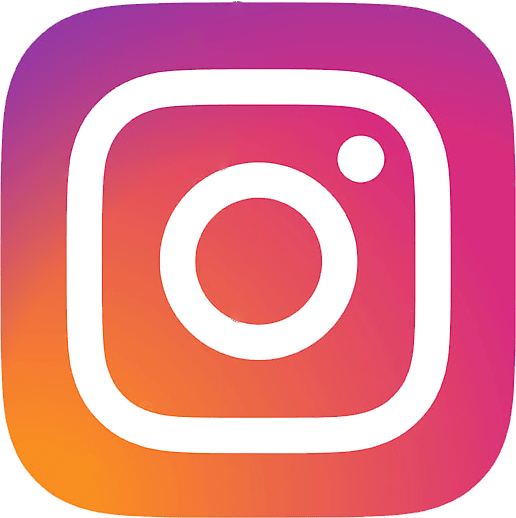灰被天目茶碗

灰被天目茶碗:元時代 茶洋窯 幅12、1cm 高さ6、5cm
骨董を買う時よくある騙し文句で、「信長、秀吉、そして利休の書と一緒にさる名家から出た」という説明でしたが、伝世の味、光の状態で虹色に光る複雑な釉肌、見込みの雲間から差し込む光を思わせる景色、高台の古い朱漆で書かれた読み取れない花押を見ると、あながち嘘ではないのでは??と思わせる何かがありました。間違いなく当時の大名や茶人が使っていたものです。本当に利休や信長がこの茶碗に口をつけ、茶を飲んだのかもしれません。しかし割れてしまったせいか本来揃っていたであろう箱も仕覆も天目台もなく、覆輪すら剥ぎ取られた姿はまるで山賊に遭って山に放り出された状態でした。たとえ栄華を誇っていても、道具を失った天目茶碗ほど哀れなものはありません。最もそういう落ちぶれた状況でなければ我が家にやって来ることもなかったでしょう。今頃はこの茶碗が本来着ていたであろう道具は状態の良い他の天目茶碗がぬくぬくと着込んで出世しているはずです。普通の家に生まれ、海を渡り、一時栄華を誇り、没落して我が家にころがり込んで来た、この茶碗が見てきた歴史を思うとおじいちゃん・・・いや、おばあちゃんかもしれないけど、まだまだこの先何があるかわからないねーと声をかけたくなってきます。
灰被天目茶碗。正直、自分にとってストライクゾーンのものではありません。しかし、一陶芸家として、伝世品を持っていたいと思いました。それは何故か。
先日、静嘉堂文庫と藤田美術館の曜変天目茶碗を見ました。幅約12cm、高さ7cm前後の膨大な数ある天目茶碗の中で、奇跡的な焼成、伝来、何より美しさにより、世界に存在する全ての焼き物の頂点へと駆け上り、不動の地位を築きました。
しかし、室町時代、その価値観を覆す時が来たのです。禅の概念の発展により、美しい曜変天目よりも、ぶっきらぼうな、飾り気のない灰被天目茶碗を最高とするムーブメントが起きました。美しく価値のあるものより、粗末なものを最上とする価値の変換。その哲学は日本が外国のコピーではない、桃山陶という、本当の意味での日本らしい焼き物ができるきっかけとなったのです。まるで1917年、マルセル・デュシャンがおよそ美術品とは無縁どころか、汚れ物の便器を美術として提示したことがきっかけで1950年代にコンセプチュアルアートが爆発的に広まったように・・・。
灰被天目茶碗は、日本における陶芸思想として最大の転換点となった、大きな意味のあるものなのです。既存の価値観に沿うことなく、その反対を行く。これは並大抵のことではありません。あれは邪道だ、あの人は常識がわからない。「こうあるべき」とつい人は言いがちです。その時点で、新しい価値観を生み出すことはできない。これは物造りにおいて安住に身を置こうとしがちな自分自身に対して、大きく鋤を入れる為の起爆剤の一つなのです。