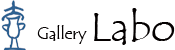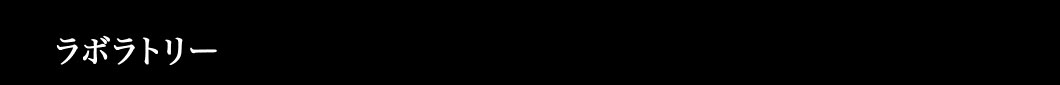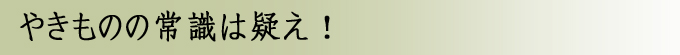「才能」や「資質」と呼ばれているものの正体は何でしょうか。
一般には両方合わせて「才能」と雑に一括りにされることが多く、むしろ「資質」のことを「才能」と誤解されていることが多いように思います。
ですが、このふたつは別のものであり「資質」は文字通り資源、「才能」はそれを何らかの形にしたり増幅させたりするための道具や手段に該当するものです。
風船を膨らませるには空気が必要ですが、「資質」が風船であれば「才能」が空気に該当します。
そのため「資質」が豊富でも「才能」に乏しいと、その逆の場合より何かしらの形を成し難いものです。
一般に「努力家」と呼ばれている人々は、相対的に少ない資質だとしても才能(「努力」は才能の中の一種です)が豊かなので、物事を形に成す確率が高くなります。「何らの資質も全てゼロ」という人は、ひょっとすれば有史以来皆無なのではないでしょうか。「器用」というのは、これまた粗雑でいい加減に使われやすい言葉なのですが、これもやはり才能の一種です。
「資質」は後天的に増大するものではありませんが、「才能」であれば認識と鍛錬次第でずいぶん増やせるものです。例えば、生来体重が豊かな人は資質、食べ過ぎや不摂生で豊かになるのは才能の成せる業です。後述しますように、もちろん前者は才能によって更に豊かになることもできます。
また、「天才」と「努力家」を反義語のように使うのは間違いです。
こういったことが定説となるのは、何をもって「努力」というのか?という解釈が様々異なりその決定的な定説が存在しないことによるのでしょう。
例えば「天才なのに努力家」などとは所詮 “外野”の言うことで、「天才」といわれる結果を出す人々は、「努力家」の人々の言う「努力」というものは実質その何倍もの密度と速度で日常の茶飯事として当たり前に行い、別段それを「努力」と感じていないだけのことです。したがって「天才ながらも努力家の面を持ち合わせる」という論評は「モグラながらもミミズを食うため土にモグる」と言うのと同じことです。
「努力家」と言われたりそれを自認する人々は、自らの資質の限界を相対的に感じ取った結果、「努力」という概念に従って修練を積む日々を送るわけですが、もちろんこれも重要な才能です。
同じ領域であれば、より早く多くのことを習得できる、またはその方法を体得するという資質が高いほど「天才」といわれる域に近付くわけなので、何事かを達成するまでのプロセスと修練すべきその内容の実際は「天才」も「努力家」も同様のものです。
ですが「努力家」の限界は、修得するまでの過程を労力と感じ、それに「努力」と命名ところにあります。
同じ体験をしても、それを苦労と感ずるか、別段何ということはないと感ずるか、楽しく感ずるか、忘我のトランス状態になるか・・という部分が「資質の差」なのです。
つまり同じ時間内に、「努力家」の努力と同様の修練を「天才」は質量において大幅に上回るわけです。
その結果があからさまに表れる場合には「天才」と呼ばれ、「努力家」とは認識されないだけのことです。
「天才」とは資質とそれを形にする道具である才能を、いずれも常人の域を超えて併せ持つ者のことを指します。膨大な資質を持ちながらも、それに見合う才能が欠けている場合は「残念な人」または「半端者」あるいは「単なる面倒臭い人」となり、結果として多くの場合「凡庸以下の者」や「社会不適応者」などと成ります。
こういった場合、「天才とそれ以外」の境界線は何処にあるのでしょうか。
これは同一の時代だけ見ても判明することではありませんので、歴史全体を俯瞰する必要があります。歴史はそのために学ぶものです。ですがそれには資料が限られ、文献史などは記述者の都合や事情により大幅な脚色が加えられているのが常であり判別が困難ですが、例えば音楽ならば自筆譜や近代以降ならば録音が無数にありますし、有り難いことにやきものは、古代以前のものから当時の状態を保って残存するものが厖大に在ります。
このように、可能な限り種々様々な分野(横軸)と歴史全体(縦軸)を俯瞰する中で「これは明らかに一線を越えた異常な能力である」という場合に「天才」と認定するのが妥当であり、これは理屈抜きに体感できるものです。
実際に「天才」はひと時代にそうゴロゴロと存在するものではありません。自分達には到底達し得ないことを次々易々と成す者を巷では安直に「天才」と呼ばれますが、これは「自分達」との比較に過ぎません。
時代の淘汰を経ていない現代の新しい分野などで世間一般から「天才」と呼ばれる人々の大半は、実質として「天才的」と形容するのが妥当でしょう。
こういったことは「記憶力」とも共通しています。
記憶は反芻の賜物であるわけですが、「記憶力が良い」といわれる人々は、そうでない人に比べて同時間内にその反芻の往復回数が多くて速度が早いわけです。発電所とコンセント間の「電圧」を連想していただけると解りやすいかと思います。
これらに共通する両者の違いは結局、“必然性”という言葉で説明できるものです。
「自分はかなり記憶力が悪い」と自称する人でも嫌な目に遭ったことは一生の間、細部まで鮮明に覚えていたりします。これに「尾鰭」が加わることも常套です。その理由は簡単なことで、忘れないのはそれを日々常に何度となく反芻するからであり、尾鰭が付くのは想像力の賜物です(想像力にも品質の差は大きいですが)。
必然性とはそういうものです。つまり、それを他事にもそのまま応用すれば「記憶力抜群」な人となり「想像力豊かな人」ともなるわけです。もっともこれらは“彼岸”と紙一重でもあるというリスクも伴い、節度と方向性を誤れば「あちらの世界にいらっしゃった人」となる場合が圧倒的に多いようなので、応用には「ちょっとしたコツ」が必要なのかもしれません。
因みに「火事場のばか力」や「締め切りに追われ尻に火が付く」などというのも必然性の仲間です。
「資質」の量は必然性の大きさと比例するものです。こういうことをこの先誰かがメソッド化して、幼少教育に採用すればこの国の義務教育も有益なものとなるかも知れません。
美術館などに一日居ても「観ている」人々をほとんど見かけないのも、この必然性の有無によるものでしょう。「観ているか否か」の判別は、怒っている犬と機嫌のよい犬との判別程度に簡単なことです。販売店来場者にも同様のことは言えますが、こちらは多くが自腹で購入するということを前提とするので迫力が異なります。現代日本は世界有数の「身腐って貝腐らん(見くさって買いくさらん)国」であり、大半の入場者や運営者にとって美術館は場末の観光地の一環にすぎません。
というわけで今回は、資質や才能と呼ばれているものの正体は必然性の有無とその質量であった、という話でした。
※注 現代の「陶芸家」と呼ばれている人々の作品からは「必然性」が感じられないことが多い、ということについては本稿の主旨ではありません。