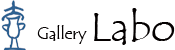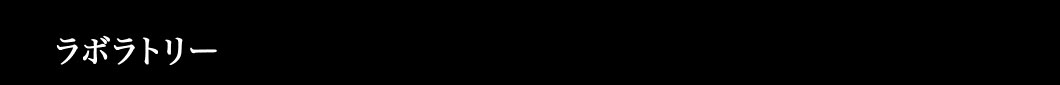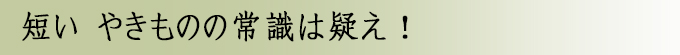その9. ことわざ ですよ
やきものに分野はありませんが、その販売店にはあります。
ふつうのやきもの店、子供用品店、婦人用品店、有付加価専門店、茶道具店、百貨店、模擬百貨店、よろず屋、古美術店と大体はこのいずれかに該当します。著名店か否かは関係なく、また決していずれに優劣があるわけではありませんが、お客さんや作者の認識に関わらず、「類は友を呼ぶ」という慣例が面白いほど当てはまっています。お客さん逹の選択には全く問題はありませんが、作者達には充分な注意が必要です。自らの志向に無頓着に、声が掛かると無節操に付き合っていると必ず「朱に交われば赤くなる」ことになります。例外を見かけることはありません。例えば、ふつうのやきものを志す作者が子供用品店と付き合うと、ほどなくその作品は中途半端なおもちゃと化します。つまり、不良品を量産することになるわけです。「餅は餅屋」と云われるように、おもちゃ屋さんに納品するには玩具製造の専門家でなければなりません。
残念なことですが、こういった分別を正確にできる作者はたいへん数が少ないようです。