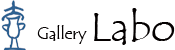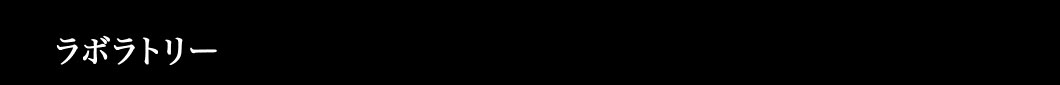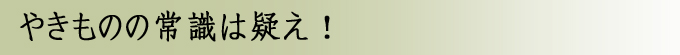「昔の陶工は無心で轆轤を挽いたので良いものが出来たのだ」、と言う人は最近でこそ少なくなりましたがまだまだ存在します。自身のファンタジーとしてはそれで良いかと思いますが、他者に口外すると「下衆の忖度」となります。下衆の忖度とは、他者の言動の動機を根拠なく自己都合で決めつけることです。「予測」に留めておくとその限りではありませんが、その場合にもやはり根拠は必要でしょう。
それでは、その「無心」について少し考えてみましょう。
お金をせびる方法についての考察ではありません。
冒頭の類の発想パターンを好む人に、「無心」というのはどのような状態のことか?と尋ねると、「上手く作ってやろうと考えないことだ」という回答がその定番です。
工人には美意識など念頭に無いと唱え教祖となった古人同様、作者に対しかなり失礼かつ短絡な決めつけだと思いますが、ではどう考えれば良いのか?と尋ねると、「何も考えないこと」と答えます。
これは結論からいうと間違いですが、良いモノを作る作者はただのアホだと決めつけていることになります。確かに、現代のやきもの作者には実際「ただのアホ」も多いのかも知れませんが、だとすれば現代陶芸と呼ばれる市場には良いやきものが溢れ返っていることとなり、そこには矛盾というものを生じます。
では、「何も考えない」ためには何をどのようにすればよいのでしょうか。
死ねばそれは容易に実現しそうにも思われますが、その裏付けを取るには”その筋の専門家”を訪ねなくてはならず、専門家を媒体としていろいろ教えてくれる彼方の世界の人々のお話からは、どうやら彼方に行っても残念ながら、「何も考えずに済む」ということは無さそうです。
それでは製作中は常に「良いモノを作るためには決して片時たりとも一切に渡り何事も考えてはならない!」と呪文のように念じ唱え続けていれば晴れて「無心」を実現できるかといえば、決してそのようにも思われません。
「うっかり」であれば、たしかに無心の一種かも知れませんが、確率からいえば失敗に直結するほうが多いように思います。「うっかりミス」というのは世間巷でよく聞かれますが、「うっかり大成功」というのはあまり耳にしません。また、製作の最中常時「うっかり」し続ける、というのは相当に高等技術だと思われ、これが達成できればすでに「うっかり」ではありません。
ならば痴呆になれば「良いモノ」を作れる、という実例は寡聞にして知らず、作成中のみ痴呆になるというのは同じく高等技術だと思われますが、何よりそれは無心好き(お金のほうではありません)の人々からは「無心の敵」と見做される、作為の極まったものでしょう。
この辺りで、そのように「無心」といわれているものの実態について考えてみることにします。
とりあえずは、「何も考えない」ということではなさそうです。
それならば何を考えれば「無心」に該当する状態になるのか?ということになります。
これは「集中」(「集中力」などと使われる集中のことです)と共通するところがあり、一点のみに意を注ぐのは「フレーミング」であり「集中」ではありません(「注意」も同様で、一点のみに注意すると四方がガラ空きとなります)。例えば「集中して観る」ということは「網膜に映るものをすべて把握する」ことです。具体的には視点が「点」ではなく「視野全面」に広がる状態です。実際の視野が文字通り拡がり、そのどの部分にも焦点が合います。これはちょっとしたトレーニングで可能なことで、けっして「気のせい」や「きつね憑き」、あるいは「自己啓発」などの類ではなく轆轤の習得と同じようなものです。
その方法については、この「常識は疑え!」のどこかで紹介したような気もしますが、ここでは割愛します。
話を戻し無心についてです。
実はひとことで言い表すことができます。
話はそこで終わってしまいますが、「無心」の正体は「余分なことを考えない」ということです。
それでは「余分なこと」とは、どういったことなのでしょうか。
冒頭であげたのが「轆轤を挽くにあたって」という一例でしたので、その例に添って考えてみることにします。
「無心」を前提とした、轆轤を挽く際に考える「余分なこと」とはどのようなことか、というのは実に単純明快で、現在作っている(挽いている)ものについて考えたり意識したりすることです。形や線をどのように取るか、口辺をどう処理するか、全体の適正なバランスは、などというのが「余分」な考えまたは意識です。作成中にこういうことを考えるメリットはひとつも無く、すべてがデメリットとなります。そのように作られたものは焼き上がったやきものに明解に顕れるものです。
では、実際に製作の最中には何を考えていればよいのでしょうか。
これも極めて実に簡単なことです。現在作成中のもの以外のことであれば何でもかまわないのです。
次に作るもの、来年つくるもの、本日の酒はどの酒器と取り合わすか、夕食のカレーに玉ねぎを何個投入するか、サルとイヌはどちらが偉いか、命令をする熊とは何か?といったことや、それらが簡単すぎて余計に気が散るようならば、『こぶとりじいさん』を漢字に直してみる、『花咲爺い』の犬はなぜ「ポチ」という名であったか?などといった歴史的時代考証などでも、とにかく今作っているもの以外のことであれば何でもよく、それが即ち「無心に轆轤を挽く」ということです。
それでは、”即今只今”作るものについては、一体いつ考案すればよいのでしょうか?
作者さんであれば、決してそのようなマヌケな質問をしてはいけません。
その日作成する土を触り始めるまで、少なくとも轆轤の前に座るまでの間、つまり日常土に触れていない時間に、やがて作るものについて細部から全体までアタマの中で完全に設計を練っておき、それが決まれば実製作に着手し、予め決めた通りそれ以上余分な考えを全て無視してただ形にすればよいわけです。注意点としては、その場で「これはマズい・・」と感じてもすでに遅く”締め切り”は過ぎていると諦めることです。
それが不都合ならば、普段の設計の精度を上げ、いつでもその場で作成できるようにしておくのがよいと思います。重要なので繰り返しますと、製作時には今作っているものについては一切考慮しない、ということです。考慮すれば即ち「無心」は消滅しますが、事前の設定が甘いと単なる「成り行き」となります。
念のためではありますが、こうやって述べているのは「無心に作る方法」であり、無心か否かなどということに全く関心が無い人であれば、作り始めてから何を作るかを決めようが、途中で次々と変更しようが、轆轤に集中しようが、轆轤の挽きすぎで首を傷めようが(この症状を「ろくろ首」といいます)、猫や鶴に代作させようが、要は「良いもの」さえ作ることができれば、その方法や手段は何でもかまわないわけです。
因みに私も「良いやきものか否か」については非常に興味がありますが、その作者が「無心か否か」などということには一切の関心がありません。
各時代の素晴らしいやきものを見ると、そのいずれにもその作者の強い作為や意図、あるいは意識の動きを見て取ることができます。
それが、美しさに類似性のある鉱物との違いであり、人間の所作としてのやきものの大きな魅力と面白さであると言えます。
「無心で作られたものこそ美しい」と信じて止まない人からは、その思考法があまりにも無心すぎて却って強烈に歪んだ作為が感じられるのみならず、無闇矢鱈に繰り出す「無心」は何かの団体の肩書のつもりなのか?ということまで「忖度」してしまう場面も多々ありますので、そういう方々には、ぜひとも無心でご覧いただければ、と願う次第です。