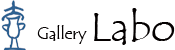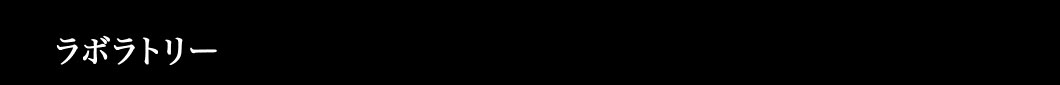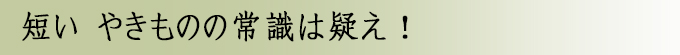その23. 美術館でやきものを見る際に最も重要な留意点のこと
『現物より先にキャプションは見ない』
留意点ならば数あれど、「究極のひとつ」といえばこれに尽きます。
せっかく見に行ったやきものから正確な情報を得るために非常に重要なことです。
やきもの関連のキャプションや解説文の大半は、机上の空論、詰めの甘い憶測、ただの誤謬、「見ての通り」のこと、曖昧な伝承や由緒伝来、残り少々が古文献の記載で占められています。見る価値があるとすれば文献資料(全てを真に受けてはいけません)くらいですが、これも「現物」より先に見ても仕方がありません。”先キャプション”によって、正確な「やきもの情報」は間違いなく大幅に削減されます。
先入観がなければ物事を見ることが出来ない、という人には他にもっともっと楽しい場所があります。
例えば、「音声ガイド」なるものに興味があれば動物園に行って下さい。オオコウモリを見ながらアシカの鳴き声を聴くと面白いですよ。美術館では、見る必要の有無に関わらず「ガイド」が喋り終えるまで突っ立たれると迷惑で無意味な渋滞の原因となります。現在の美術館は観光産業なので仕方がないのでしょうが、美術館員は元より展示物に大した興味もないのか、こういうバカ製造機を「普及」の名のもとに導入し日銭を稼ごうとします。