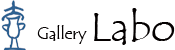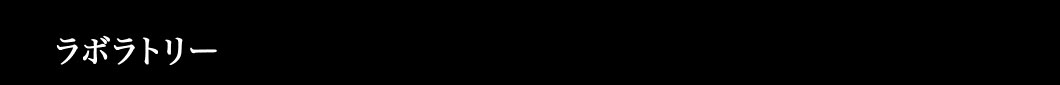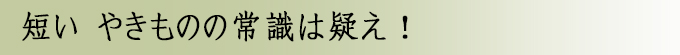その29. 高台です
やきものの本をみると、「高台は茶碗の心臓、要、生命、高台がダメな茶碗はダメ」等々、その重要性について書かれているのを目にします。果たしてその実態は如何でしょうか?
高台は茶碗のケツです。
茶を喫した後、ひっくり返して眺めますね。つまり起承転結の「結」です。何のケツだと思われましたか?
実際には高台は無くとも器として成立しますので、「心臓」や「生命」ではありません。前回(28.)述べましたように、茶碗を含め器の生命は「見込」です。良し悪しは別として、これが無ければ器ではありません。因みに心臓にあたるのは「材質感」だと思っています。
やきもの好きは、茶碗でなくとも、酒盃、茶入、花入、大壺・・とにかく何であろうが、先ずひっくりかえして「ケツ」を眺めます。「結」も何もあったものではありません。つまり鑑賞の上で、先ずはとても気になる部分だということです。たいへん尤もなことで、賛成に一票です。
つまり「面食い」の人々にとっての「顔」に該当するわけです。やきもの好きは、ケツこそ顔なのです。
やきものを作ることを「作陶する」といいますが、やきもの好きは「倒錯する」ものでしょうか。