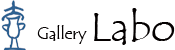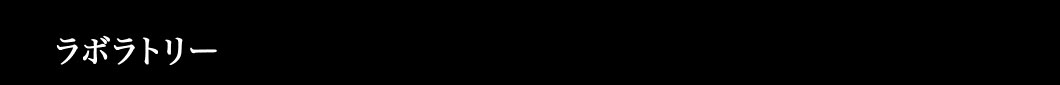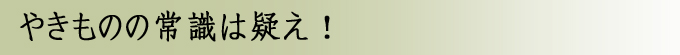「ぐい呑は酒呑みの作ったものが良い」「酒を呑まない作者のぐい呑ではダメだ」 と言うやきものコレクターが、かつてこの国のバブル経済期には多数存在したものです。最近でこそあまり見かけなくなりましたが、そういった先達の言葉は今も痕跡を残しているようです。
果たして、それはほんとうのことなのでしょうか?
ウソです。
以上で本稿の役割を終えましたので、下記はあとがき、または参照です。
明代以前の中国や李朝などのものには、酒盃として大変優れたものが古陶磁にも多数ありますが、これらはその作者が「日本の酒」を呑みそれに合う器を作ったものではありません。その大半が元より酒器ではないものを我が国の愛好者が見立てたものです。
そういった「酒器」が近代以降ブランド化され、その価格が「1000回使っても一回あたり1.000円」は当たり前、という状況は既存の付加価値に踊らされる者が多い世の常だとしても、実際それらをぐい呑に見立てると壮絶な威力を発揮するものです。
我が国の近世以前のものにもやはり一回1.000円ブランドはいろいろありますが、それらのほとんども出自がぐい呑ではなく、中附や小碗などに生まれたものです。
また近世以前のそれらの作者が仮に大酒呑みであったとしても、その酒は現在の「日本の酒」とは異なる酒です。
酒を呑む器として「ぐい呑」が作られるようになった近現代では、大酒呑みで知られる作者には良いぐい呑を作る人もあれば、全くそうでない作者もあり、酒を一滴も呑まなくても良いぐい呑を作る人もいれば、全くそうでない人もいます。
酒呑み作者か否かと良いぐい呑の間には、その因果関係がみられません。
まずは、大酒呑みが作るぐい呑の功罪について考えてみます。
大酒を呑んで轆轤を回すと世界も共に回りますので、そこに地球の自転が加わり三重構造の回転軸となります。それぞれの回転がぴったり一致することによって名品が生まれます。
ですがそれが少しでもズレると『ぐい呑千鳥足』という演歌のタイトルのようなものになります。
それぞれの回転軸とその軌道が正しく一致するのは三十八年に一度といわれていますので成功率は高くありません・・・というのも冒頭と同じウソのサンパチです。
酒呑みの作者は、意識、無意識にかかわらず「自分の酒」に合うものを作りがちです。
自分の酒とは、呑む酒、その状況、心理、間合い、酔っ払い方、合わす肴の有無や嗜好など、それぞれが異なります。
そうなれば、酒好きの作者が自らの酒に合うぐい呑を作ることに成功すればするほど、使う側がその作者の嗜好性と合致しない限り邪魔や欠落する部分が多くなりますが、それ以前に生理的拒絶反応を覚え、蟹嫌いが「かに道楽」に連れて来られたようなことになります。
大酒飲みでも、ぐい呑を作る際には「ぐい呑」ではなくそのくらいのサイズのやきものを作る、ということに徹するという作者もいますがかなり少数でしょう。
酒呑み作者と使用者との嗜好が見事一致!という「運命の出会い」もあるかも知れませんが、ほとんどは見る側の感度の故障、投影や関係妄想という病気の一種、そして案外多いのが「ぐい呑コレクター」であっても酒とやきものには大した興味が無い場合のいずれかでしょう。
そのようなわけで、酒呑みがぐい呑を作る際にはぐい呑であるということを無視する、言い換えれば「ぐい呑を作る際にはぐい呑を作らない」のが最良の方法です。
そうすると放っておいても「酒の妖精」の功徳により、これまで呑んで来た酒量に応じて良いぐい呑が勝手に「降りて来る」かもしれません。
そういうことこそ「ほんとうの無心」あるいは「正しい作為」というのものなのでしょう。
酒呑み作者の「俺様専用」は、別枠にて自分自身の受注生産にすればよいと思います。
それでは次に、酒をまったく嗜まない作者がぐい呑を作る際の注意点としては、どのようなものがあるでしょうか。
これも酒呑み作者と同様で、「ぐい呑を作る」ということを一切念頭に置かないのが最良の方法です。
呑まない者が、酒呑みがぐい呑のどういうところに見所を置くか?などということは決して配慮しないことです。
ぐい呑の楽しさ、使い勝手の良さ、といったものは決して理では割り切れないものなので、考えても無駄です。机上の空論、余計な親切大きななお世話、媚び諂い、下衆の勘繰りといった、いわゆる「いやらしいもの」になる可能性が増大します。
酒呑み同様、適度な寸法の良いやきものを作ることを前提に、作成時には「桃太郎の入った桃を川から引き揚げて洗濯板や未乾燥の洗濯物と共に担いで帰った婆さんの背筋力」と「帰宅した爺さんが未知の大桃を鉈で叩き割っても無傷で元気な桃太郎」などについての考察を巡らせながら作れば、良いぐい呑が出来る確率が上がると思います。
酒呑まぬ者は、酒の妖精の助力を期待できないぶん、酒呑みに比べ雑念や他力依存を排除することが容易です。「下手(下戸)の考え休むに似たり」という格言もありますので、「使い勝手」や「呑みやすさ」など余計な妄念さえ抱かなければ、実は酒呑まぬ作者のほうが良いぐい呑を作るには有利なのです。
そのようなわけで、酒呑み、下戸にかかわらず作者がぐい呑を作る際、良いやきものに必要な素材を選択し、姿と手重りを決定するところまではその他の器種同様ですが、ぐい呑の場合選択はそこまでです。
繰り返しますが、ぐい呑を作る際決してやってはいけないのは「呑みやすさ」への忖度です。とにかくこれだけは下手にやってはいけません。
下手な配慮のほとんどは「あからさま」なので、親切心ではなく物乞い根性を思わせるものです。
呑みやすさへの配慮は、蛇足に蛙臍です。
呑みやすさや使い勝手に媚びない、ということはぐい呑作りにおいてほんとうに重要なことです。
内部や口辺部のみに釉が掛かったり、見込のみの白釉が「酒の色見」であったり、取って付けたように口辺の端反りや薄い、などというぐい呑は、鼻の高低にかかわらず鼻につくものです。
呑みやすさや手取り感に配慮を加えるのであれば、説明さえしなければ呑み手には決して気付かれることのない様々な配慮を仕込むことですが、相当に高等技術なのか多くは見かけるものではありません。
とにかく、ぐい呑が「呑みにくい」などといってもたかが知れたものす。 良いやきものであってサイズが適切であれば、それが即ち「呑みやすいぐいのみ」ですが、やきものとしてダメならば、あとがどうであろうとも「呑みにくいぐい呑」です。先ずは触る気がしないからです。
また、「焼締めのぐい呑には口をつける気がしない」などと言う人もいますが、「虫には触る気がしない」というのと同じことなので、こういった話に取り合う必要はまったくありません。
呑む側が「呑みやすさ第一!」とするならば、100均に直行すれば解決されます。加えてこれならば「10回使えば一回11円(税込)」で済みます。
ぐい呑に「用の美」なる曖昧さは通用しません。やきものとして如何か、がすべてです。
その他に留意する点があるとすれば「漏れ具合い」です。 注いだそばから次々と外出してしまうと、せっかく濁り酒を買ってきても、注ぐ傍から濾過されて次々と清酒になって出てきますので、わざわざ濁り酒を選んだ意味がなくなります。漏れ具合いが丁度よいぐい呑であれば、温度管理を慎重に行うと「袋吊り酒」と同じ効果が得られるかもしれませんが、最初から良い袋吊り酒を買って来るほうが良いと思います。
「チョイ漏れ」のぐい呑もなかなか良いものですが、注意点としては、チョイ漏れ片手に本などを読んでいると、ページが知らぬ間にヨレヨレになったりする恐れもあります。
「ダダ洩れ」のメリットは机や盆が育つことくらいですので、すでに充分に味の良い机や盆をお持ちの方には必要ありません。
いかにも漏れそうな土肌ながらも「漏れナシ」でも一向に構いませんが、無理に漏り止めを施すくらいならば少々漏れてもそのまま使うことを推奨します。
荒土特有の質感が好きで求める器は、ある程度の漏れがあるのが自然です。撥水剤にドブ漬けされたぐい呑は水通ししても雨カッパのように表面に水滴がいくつか残る有様となります。
こうなると漏れずともやきものとしての価値や魅力は半減以下となり、また洗っても落ちず、焼き直すと白濁皮膜が残るものもあるので、雑な撥水は絶対にやめてもらいたいものです。 このあたりも作者のやきものに対するセンスが現れる部分です。
こういったことになるのは、やきものにさほどの興味も無い販売者が、同じく興味の無い顧客からのクレームにより、同じく興味の無い作者が隷従する、という弊害の連鎖だといえます。
漏れ具合いならば、後から好みに応じていろいろと調整できます。
話を戻します。 上記のように、良いぐい呑は「良いやきもの」であるというのが必要絶対条件です。次が寸法と手取り感で、これらに問題なければ他に条件は特にありません。
もちろん他機種も「良いやきもの」である必要があるものの、ぐい呑は手に取っての使用時間が飯碗や向附より大幅に長く、日々酒を嗜む者にとって身体の一部ともいえるやきものなのです。
「ぐい呑は小型の茶碗」だという人もいるようですが、とんでもないことです。 作者がそう考えて作ったとすれば、それは「茶碗フィギュア」または「茶碗もどき」であり、そういったものをぐい呑に見立てると厭らしさが滲み出るものです。そのような作者や愛好者はぐい呑をナメ切っているのだと思われます。
これからぐい呑と生活を共にする方々は、決してそのような「たわ言」を真に受けてはいけません。
一見いかに姿形に共通点があったとしても、ぐい呑と茶碗は全く性質の異なる器です。用途や大小ではなくやきものとしての本質のことです。
強いて言うならば「ぐい呑の大型が茶碗」というほうがまだしも妥当であり、強いて何の小型か?となれば、形状や寸法はともかくとして本質的には「壺の小型」かもしれません。
茶碗で酒を呑めばどこまでも「茶碗酒」であり、ぐい呑の代用ではありません。
いずれにしても、やきものは品質と品格において、小さなもののほうが大きなものより作成の難易度は遥かに高くなりますので、「茶碗の小型」などと軽視していれば、当然のことながら良いぐい呑は生まれません。
「茶碗は格が高いので軽視などしていない」という人は、やきもの全体を軽視しているのでしょう。
やきものには器種別の「格」の高低、上下などという格差は一切ありません。 茶の湯の稽古などで道具の格の上下などを教えられたとすれば、それは階級制度の名残りかもしれません。
茶碗の値段がぐい呑より高いのは「業界の伝統」ですが、ぐい呑も大きさが同じくらいの小皿より一般に割高のようですが、これも小皿がやきものとして「格下」だからではなく、市場の原理です。
「格」に上下があるとすれば、それは品格のことです。
これについては個体による高低ならびに上下 差が明確にあります。品格差の判別は、差別ではなく区別です。当然その査定基準は、見る側の眼の品性に依ります。
本来はこの品格が価格に反映されるべきものですが、そのようにはなっていません。
外国人観光客が押し寄せると、宿泊交通費などが法外な値段になり自国民がとんでもない迷惑を被るわけですが、観光業者と国家は潤います。繁忙期にここぞと法外な値段に吊り上げる手法は近年目立って急増していますが、下劣な品性が蔓延し下向へと辿る国の資本主義経済の根幹なのでしょう。
同様に陶芸という零細業界内でも、ぐい呑が流行れば、先述したように投機転売目的の者や外国人を含め、如何なる世相にも簡単に流される俗物が増加し市場の多くを占めるようになるので、観光同様、業者がメディアと共に強引に偽ブランド化させ不当な価格とする乞食の原理、否、市場の原理が横行します。
それに従うならば、茶碗はその需要を激減させ続けているので、市場の原理に従えば価格が下がってもよいと思いますが、ぐい呑が主力商品となってしまった現状ではそうはいきません。
こうなると一見どうにもならないように思えますが、そうでもありません。
業者と作者が至極真っ当に、「その気」にさえなればある程度は食い止めることができるのです・・・が、「その気」を詳説公表すると、近年流行の「ダイヴァーシティ」や「コンプライアンス」(なぜこういったことを自国語で言えないのでしょうか)の阻害となりますので、勝手に黙って実行を心掛けることにしています。バカなことには感化されず盲従しないのは民主主義本来の姿だと思います。
「ぐい呑以外は買わない(ぐいのみのみ)」という人はぐい呑をみる眼も甘いという例を巷に多く見かけます。これはたいへん残念で勿体ないことです。
安直な「ぐい呑展」というものが蔓延りそれを助長し、ぐい呑を単なる売れ筋アイテムへと成り下げています。例外なく、その内容構成からは百貨店の産地物産展ほどの整合性もみられない寄せ集めものを抽選で売っているわけです。作者に実際に来る「企画書」は、点数と納期と掛け率だけです。このようなものに参加する作者にも問題があります。
新規生産されるぐい呑の量は相変わらず増え続けていますが、それに伴って良いぐい呑の数も増えているわけではありません。
好みは個々それぞれであっても、やきもの全体を見ない限りぐい呑の最も重要素である「やきものとしての良さ」の判別は不可能です。
実際、良いぐい呑を選ぶ精度の高い人がぐい呑しか買わないという例を知りません。
ぐい呑コレクションの品質を向上させたい、という方に最も推奨できるのが、まずはぐい呑以外のものを買ってみることです。
もう少し具体的に言えば、その場合には壺が最も確かな効果が望めます。
とにかく、冒頭のような文言や、その流れで業者とメディアがでっち上げる「酒器の名人」「酒器の神様」などという、選挙ポスター並みのキャッチフレーズには引っ掛からないことです。
常々述べているように、陶芸関連メディアの情報で実際の役に立つものはありませんので、予備知識と先入観を排して自らの眼で選ぶということに尽きます。更には、このような文章をここまで読む暇があれば、先ずはぐい呑一点でもいいので良いやきものを選び共に時間を過ごすことをお薦めします。
もしその場では「買って失敗」と感じても、後に必ずそれが糧になります。
その際の留意点としては、買った後「失敗した」と思っても決してキャンセルや返品はしないことです。
これをする人は”眼”も”人間”も決して向上することはありません(因みに古美術のほうではこういう人を「ションベン野郎」と呼ぶそうですが、実質よりも穏やかな隠語だと思います)。転売屋でなくとも「失敗」の場合はすぐに転売せず、しばらくは手元に置くことです。資金不足であれば「失敗でないもの」を売却することです。
事態の是非はさて置き、先述のように新陶古陶や国内外を問わず、ぐい呑がやきもの市場に占める割合を増し続ける近年です。
そういった購入者の全員がやきもの愛好者というわけではないにせよ(実はそこも問題ではありますが)、それでもぐい呑が本来「良いやきもの」としての使命を背負っているということを、ぐい呑を求める人々の多くには潜在的に感知されているのではないかとも思っています。
現代ではそのように、ぐい呑が否が応でも「やきもの大使」に任命されているので、ぐい呑を作る作者には最初にぐい呑より入門した人々がやきもの全般に興味を広げることの出来る力量が求められます。
したがって、ぐい呑に良いやきものとしての実力が備わっていなければ、数多のぐい呑専門コレクターの「目筋」は、やきものを専らネットオークションで安物処分品しか買わない人と同様に向上を望めず、やきもの業界の質も下向の一途を辿るわけです。
やきものへ興味は人類の歴史への興味へと直結するので、作者や業者の責務は重大なものです。
本稿は、ぐい呑の良否は作者のやきもの全般への興味の度合いとそれを形に成す精度が主要因であり、その作者が上戸か下戸かあるいは無戸か?ということとの因果関係はなく、使う側がそれを留意する必要はない、という話でした。主旨はこの三行のみであとはすべて余談です。
※余余談. 本稿で敢えて記載使用した「ぐい呑(ぐいのみ)」という言葉は、”話し言葉”としてのやきもの日常会話において違和感を感じませんが、”書き言葉”となれば途端に品が無く感ずるので通常の使用は控えています。作品名や箱書きにそのように書かれていると、その作者の自己が表現されたものと解釈しています。 なお、本稿で取り上げた「ぐい呑」とは広義にて酒を呑む陶磁器のことで平盃形その他も含みます。
※余余余談. 日本の酒が日本酒(にほんしゅ)と呼ばれるのは、わが国が敗戦国だからなのでしょうか? 「普段何を呑んでいるのか?」と尋ねられ「酒」と答えると「にほんしゅ?」と問われ、「否。ワインはワイン、ビールはビール、ウォッカはウォッカ、ウイスキーはウイスキー、酒といえば酒である。『日本酒』などと卑屈な言葉を発するではない!この非国民」などと答えようものならば、ただでさえ少ない知り合いを更に失うことになるので、そういった愚問はぜひともやめてもらいたいものです。
(因みに私は国粋主義者ではありません。)