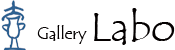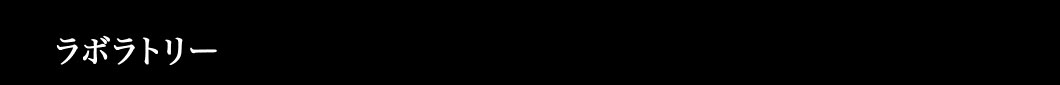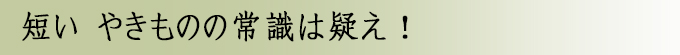33. やきものレトリックにご注意 其の三
茶碗は「やきものレトリック」の宝庫ですので、今回はNo.25につづく茶碗の二回目です。
「茶碗を作るのであれば茶の稽古を十年は積まなければならない」と言う人達が、かつてはたくさんいたものです。 それはほんとうでしょうか?
高麗茶碗には優れた茶碗が数多いものですが、これらの作者が茶の湯の稽古をしていた様子はありません。わが国の茶の湯全盛期であった時代の茶会記を見ても、陶工が出席している様子はみられません。
近現代の陶芸家といわれる人々には盛んに茶の稽古に通う人が多いようですが、上記の陶工達の茶碗を越えるものはあまり見かけません。
そもそも、茶事(大寄せ月次釜は茶事ではありません)を頻繁に行わない稽古は茶の湯ではなく”お稽古ごと”に過ぎません。すべての所作や点前は茶事のために存在します。陶工さんが茶事を行なわない稽古場などに通っても、もちろん良い茶碗は出来ません。ましてやそれが「顧客」を増やす目的ならば、やがて確実にその作品には卑屈さを帯びるでしょう。やきものにも少数の本物と大量のニセ物があるように、茶の稽古も同様なので、関わる際にはそれらを判別する目利きも必要となります。
そのようなお金や時間と労力を費やすならば、まずは真っ当な茶碗をひとつ買って日々使ったり眺めたりするほうが遥かに効果が望めます。茶の稽古に通わなくとも、茶碗と湯と茶筅があれば茶は点ちます。
仮にもしも奇跡的に素晴らしい茶の師匠と巡り合えたならば、茶の湯自体は学ぶところの多いものなので入門すべきですが、稽古の際には自らが茶碗を作ることなどは完全に棚上げし、ただひたすら茶の湯を修練することを勧めます。