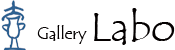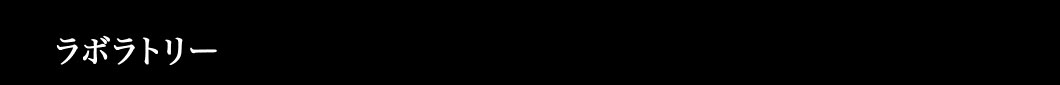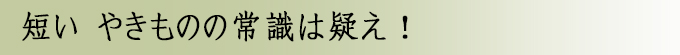その34. 備前茶碗は何故少ないか
茶の湯隆盛期に備前の茶碗が少なかったのはなぜでしょう。
因みに近現代は何でもありなので、備前作者の多くが茶碗も作っています。
備前の茶碗が少なかったのは主に二つの理由があります。
ひとつは他の道具との取り合わせの都合によるもの(詳細は少し長くなるので省きますが本編のどこかで述べた記憶があります)。
もうひとつが備前陶は熱伝導率が高い、つまり湯を入れると熱いということです。熱いといってもたかが知れたもので軍手が必要なほどではありませんが、当時の茶碗の大半は熱伝導率の低いものが取り上げられています(同上)。
語られることの最も多い誤りとして「茶筅が傷むから」というものがありますが、正しく使っても茶筅が傷む場合は、見込の成形、焼成、仕上げに難があるわけで、これはなにも備前や焼締め陶ならではの特徴ではなく、そいういった茶碗を選ばなければ解決する問題です。正常な備前茶碗であれば傷みません。
見込が大小の降りものだらけで手入れも甘く、茶巾は即刻糸屑となる「見込が枯山水」でない限り、すぐに傷むのは茶筅を振るのが下手なだけです。濃茶でも、見込がツルツルでないほうが軽い力で練ることができます。振りや練りが下手で雑だと、釉ものでもピンホールに茶筅を取られます。
そのようなこと以前に、茶筅は本来使い捨てのものでした。
備前茶碗を一様に「見込が傷む」という人をみるたび、海鼠を最初に食べた人の偉大さについて想念します。