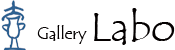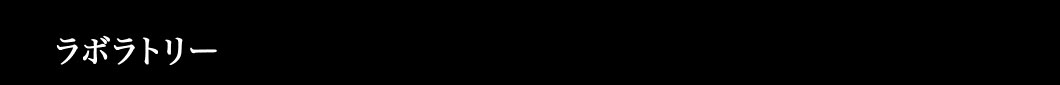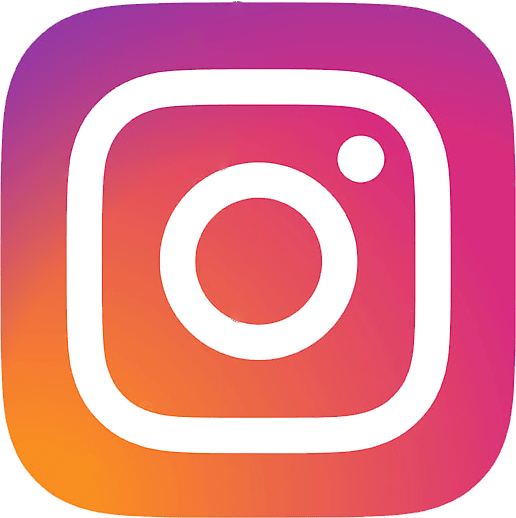やきものを焼くには通常、窯を使います。
穴窯、登り窯、あるいはガス、電気、灯油などを燃料とする窯のことです。
それぞれの窯にはそれぞれの構造があります。
“窯の構造”によって、出来る作品が違うそうです。
なぜ窯の構造によって出来る作品が違うのでしょうか?
その構造によって「火の回り」が異なるからだそうです。
たぶんそういうことなのでしょう。
ではその“窯の構造”とは何でしょうか?
たとえば、「穴窯は単室で火のまっすぐ抜ける直焔式」、「登り窯は“間仕切り”があり火が回る倒焔式」などといわれています。
確かにそれらの窯をみる限りにおいて、それらの説にとりわけ疑問を持たなくてもよさそうにみえます。
ですが、ここにはひとつ重大な見落としがあるように思います。
窯詰め、という作業があります。やきものとなる成形素地を窯に入れる作業のことです。
多くの場合、この窯詰めの仕方によって出て来るやきものの景色や出来具合いが左右されるといわれます。「やきものは窯詰めで焼いておけ」という古人の言葉も遺されています。
窯詰めによってやきものの仕上がりが異なることは間違いのないことです。ですから窯詰めはやきものの作成行程において特に重要な作業です。
ここで述べようとしているのは、それとはまた異なることについてです。
製作者にとって、窯に詰めたものはやきものとなる作品です。予定する焼き成りにより近づけ、またはできるだけ“ロス”を出さぬよういろいろと工夫するわけです。それは至極当然のことです。
ではここでの「見落とし」とはどういったことなのでしょうか?
上記のことは、いずれもやきものを焼く人間の立場からみた視点です。ですが実際に「窯の中に入ってせっせと働く」のは、火つまり熱エネルギーや炭素や水素やアルカリなど(以下、火と略称)です。
では、彼らにとっての「窯」とは何でしょうか。
窯焚きの最中、窯に入って作業する担当者である“火”の実務行程をひとことで言えば、入り口から入って出口より出る、つまり「焚口より入って煙突から出て来る」ことです。
人間側からいう窯焚きとは、彼ら実作業者に的確に実務指示を出し監督する仕事のことであり、窯詰めはその作業環境を予め整えておく仕事でもあります。
彼らがその途中で出会うものに引っ付いたり離れたり、そこにしばらく滞在したりを繰り返した結果、「中にあるもの」はやきものとなって出て来るわけです(正確にいえば出て来たりはしません。鬱になろうが不眠になろうが、嫌でも引っ張り出さなくてはなりません。「窯出しが楽しみ」などという者は、外野の見物人でなければ、バカか超天才かまるっきり初心者のいずれかであると思われます)。
話がやや逸れそうになりましたが、結論を述べますと火が途中で出会うものの全てが「窯」の正体です。つまり、外にいる人間にとっての「窯と作品」は火にとっては「窯」です。
普段見かける“中が空”の状態の冒頭で述べたような「窯」は、建築物にとっての屋根と外壁にすぎません。居住空間などにおいて柱、廊下、間仕切り、調度品や生活用具などを備えたなかでの住人の動線にあたるのが、窯焚き最中の火の動きなのです。
簡単な例を挙げてみますと、「穴窯」の中ほどに「作品」で壁を作って仕切れば、たちまち“登り窯”となり、また「登り窯」の上部を「作品」で密集させると“穴窯”に近い動線となります。
そしてこれが本稿の結論ですが、「窯詰め」という作業のその実は「築窯」に他ならぬものであるということです。したがって「窯の構造」とは、主に窯詰めされた内部の状態のことを指します。
窯詰めという作業のたびに毎回、窯は別のものに築き変わっているわけです。