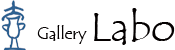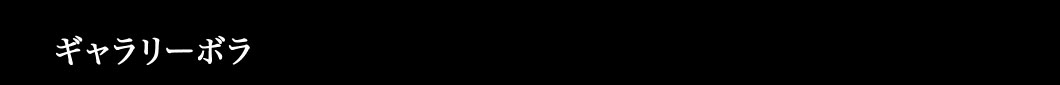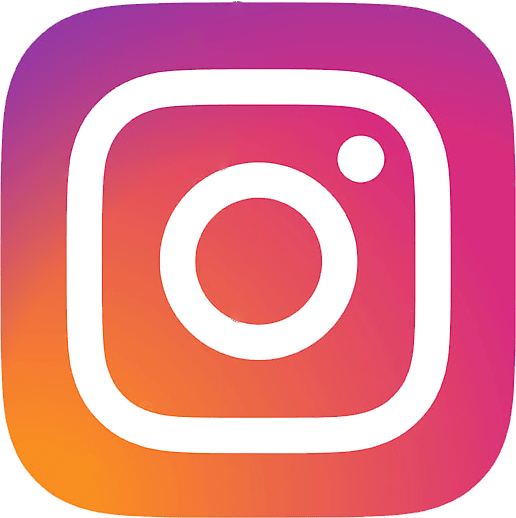第十回 「向き不向き」について
才能と資質とは混同されることがあるが、これらは別のものである。
資質とはそれぞれの個体に生来備わるものでありそれ単体で機能するものではなく、才能とはその資質を形に変換する能力のことであり、資質と才能は何かしらの成果に不可欠なパートナーといえる。
資質、才能ともに豊富であれば十全であるが、資質が多く才能が少ない者よりも、資質の埋蔵量は少なくともそれを発掘し形にする才能の豊かな者のほうが「結果が出る」ものであり、例えば努力、実行、構成、編集など各能力の量は後天的な「才能」で増幅できるものである。
体が大きくて力持ちというだけでは相撲取りにはなれず、知能が高いだけでは世の役には立たない。
「向き不向き」という言い回しがあるが、これは通常「資質」とそれをを形に出来る「才能」の有無を混同して使われるが、これは通常目に見える成果より判定されるものだ。
実際の傾向としては「向いた者」はなぜそれがそこまで出来るのか自分でもわからず、「向かない者」はなぜ自分は出来ないかがわからない、といった特徴がみられるが、特に後者の場合ではまず、自分が出来ていないということに気付かないという事態を伴う場合が多いようである。音痴は自分の音が外れていることに気が付かないので音痴であり続けるものだ(気付く場合は修正するか歌うのを永遠にやめるか、または開き直るかの三択となるが、後者は環境を著しく害する)。
本来「資質」をある程度備えた者は「才能」を研鑽する義務を生ずるが常にそう好都合にはゆかず、このように人類にとって実際に肝心なことには法的拘束は無く、「民主主義国家」にはその教育システムも無い。
やきものの業界をみていても同じことが言え、作者の場合であれば作品が大したことないこととその作者の自負心の大きさは比例し、愛好者であれば目筋の悪さとやはりその者の自負心の大きさは比例する。因みにこの場合の自負心とは、「自分の作品は良く出来ている」、「自分は多くを見てよく知っている」などという類の自己認識のことである。この時点でその者の資質の限界と才能の放棄が顕著となり、「知らないということを知る」という人間の品性や今後の展望を大部分を司る機能が停止し、結果として「それで終わる」わけである(尤も、終わっていても村全体が終わっていればそれが村の常識となるものだ)。
やきもの業界も現在のこの国同様、近々『猿の惑星』や『ゾンビ』が映画ではなく同様の現実となるとしても、やきものは古代より歴代のものを手に取って熟覧できるのである。つまりたいへん幸いなことに、やきものの世界にはやきものが有るのだ。
なので『有志』の方々は決して偏った見方や趣向、メディアの情報などに捕らわれず、現代陶が後世から通観して恥じる品質とならぬよう邁進を望むが、これにはやはり先ず「出来ていないことを知る」「知らないということを知る」ということが前提として必須である。
そのための方法は簡単で、先ずは自らの「知っている」「出来る」「好き嫌い」「良し悪し」といった基準を徹底して疑ってみることである。そして古来言い古されたことではあるが、そのための時間と金銭を惜しまないことだ。元より、練られることなく精度の低い自尊心やアイデンティティーなど無いに越したことはない。
「将来の設計を・・」などと言っている間に将来は着々と終わり続け、その「将来」はそうやって蔑ろにされた「只今」によって報復される。