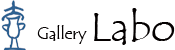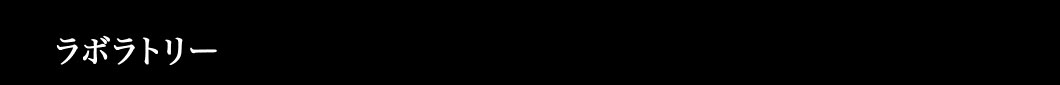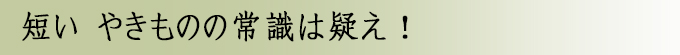その24. 「やきもの」と「陶芸」の違いについて
やきものとは、人間に土や石が焼かれて何らかの形を成したものです。
やきものを作って焼くことは、「作陶」(陶磁器製作の略語なので”磁器”も該当します)といわれます。
では、なぜ「陶芸」という言葉が出現したのでしょうか。
「陶芸」は昭和以降、生活必需品(「必需」は人によって随分異なるが)としてではなく、趣味の愛玩物を目的とした作陶行為を指すようですが、その後一般に浸透したようです。
それらの違いについての基準が明示された実例をみないので、勝手に区別することにしています。
自己表現を目的とした作陶行為を「陶芸」、それ以外のものが「やきもの」です。
実に簡単な区別ですがそれでよいと思います。図らずも結果として「自己表現」となっていたとしても、それが実際に作者の目的でなければ「やきもの」です。
念のため、これは決して「どちらが良いか?」ということではありません。
自己表現として「陶芸」を志す者はまずはその前提として、いちど焼くと向う数億年は土に還らない素材を扱うに値するだけの、地球という存在に対等の「自己」を形成する必要があります。技術以前に先ずその人間そのものを問われることになりますので、これはなかなか大変そうです。「陶芸家」は自己申告制といえど、”人生の成れの果て”とも云われる「陶芸家」による真っ当な陶芸というものになかなかお目に掛かれないので、やはり「超人」の出現を待つより他になさそうです。