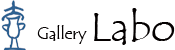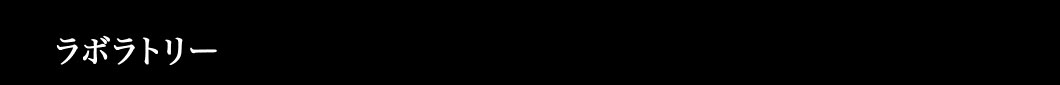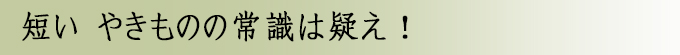その31. 手間な話
「手間暇」とは何でしょうか。
「これだけの手間がかかったのだから、これだけの対価を貰わなくては」という作者は少なくありません。
そういう作者はダメな作者です。
「手間」という発想が、すでに自発性を失した労働という認識となっていて、もちろんそれは作品に反映されます。いかに精緻な造りでもやきものとして魅力がなく、公募展の審査員くらいにしか喜ばれない数多の作品は”手間暇の産物”なのかもしれません。
やきもの愛好者が評価し興味の対象となるのは、やきものそのものであって手間暇ではありません。
作者たちもその「手間暇」こそが即ち、わざわざ志して生業としている作陶という行為であるわけです。
将棋などは、平時本番共にとても手間でたいへんそうに思われますが、手間暇かけた者の勝ちではなく手間暇を売りにする者もいません。相撲取りも稽古の質量は結果に反映されるものの、稽古時間による星の加算や、膨大な稽古の末に負けが込んでも「努力賞」はありませんし、ケガをすれば休場や引退あるのみです。これらは、「手間暇」なるものが生業または生活そのものであり、取り立てて言うに及ばないものだからです。
やきものも、買う側にとってそれが「良いやきもの」であるということ以外に、支払う対価はびた一文も無いのです。
世には決して「時給換算」など出来ない仕事もある、というごく当たり前のことも忘れ去られつつある現世のようです。