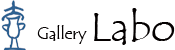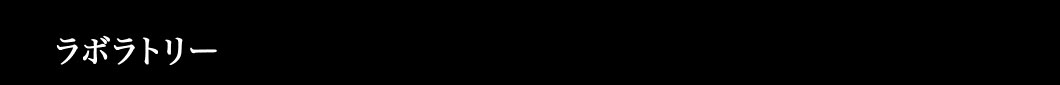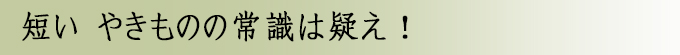その32. 手間な話 其の二
前回は「手間暇」という認識を元手に作陶する作者はダメですという話でしたので、それでは認否にかかわらず、やきもの作者という生業における「実質上の手間暇」とは何か?について考えてみることにします。
先ずは、公共交通機関などによる個展会場への移動や宿泊の手配ですが、これはいかにも面倒臭そうです。もし自分が作者さんの立場ならば、これが最大の手間暇だと思います。次に原料である土石採掘にあたって変人の多い地権者との交渉なども、疲労困憊が予測されます。また窯焚きなどしていて、あとから引っ越して来た近隣住民による苦情への折衝はさらに気力を浪費することでしょう。
また、現代の作者は有史以来の先達の仕事を「知らない」では済まない(実際にそういったことを知らない素人でも人気作家となるのは”陶芸”業界くらいでしょうが)ので、「資料」を次々購入することで持ち金がどんどん無くなるのは止むを得ないにせよ、持ち金ではどうにもならないものを美術館などに見に行こうものなら、館内の「観光バス内」の如く空気感や「動物が顔だけ出した動物園」のような展示状況により、虚無感を伴う重度の疲労が確約されています。
見ていて作業全行程で実務として最も手間暇が掛かりそうなのが、窯から出した後の「手入れ」の作業ですが、これは商品として出荷するのであれば仕方のないことです。加えて、繁忙期に手伝わせる猫を日頃から訓練しておくことも必要です。
やきもの作者に想定できる手間暇としては、これくらいで全て網羅したかとは思いますが、さてこれらの中で、その手間暇を直接価格に上乗せできるものはどれでしょうか?
せめて、その価格に「子供の塾の月謝」が入っていないことを祈ります。